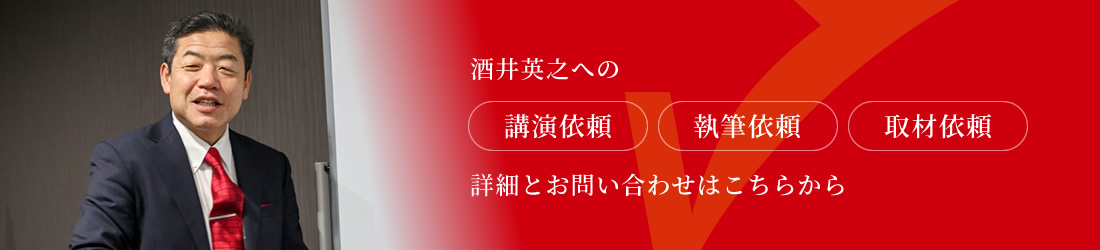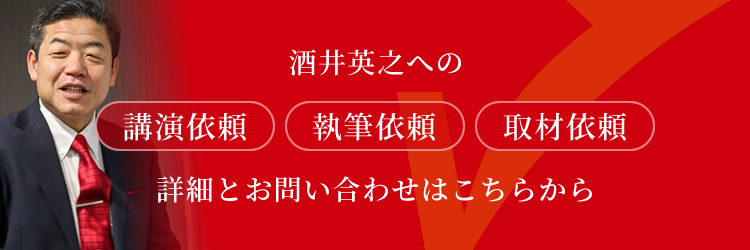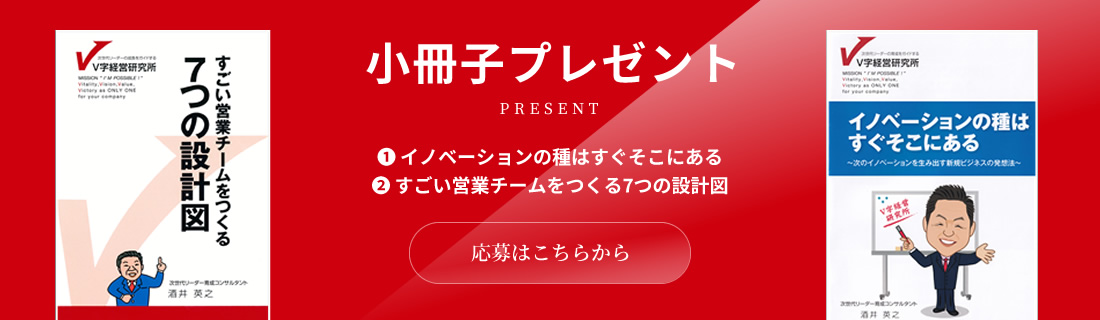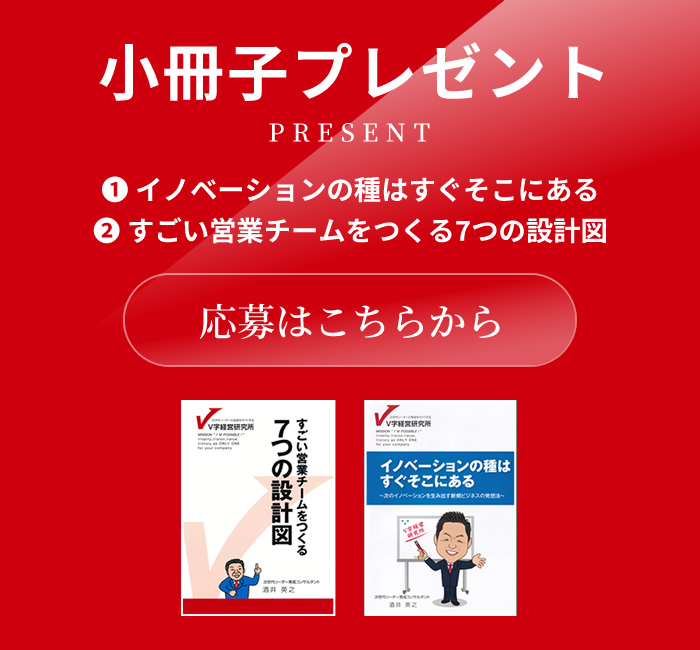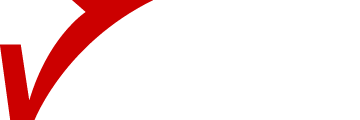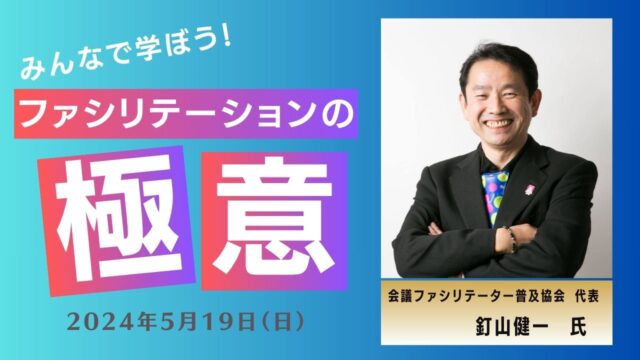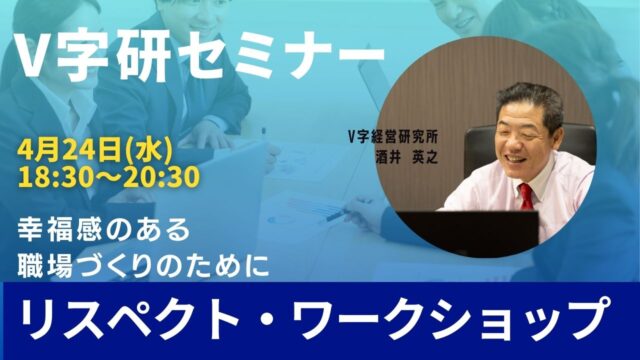理念は「わが社はどうありたいか」を言葉にしたもの。
ビジョンは「わが社は何を創造したいのか」を示したものです。
理念とビジョンはいついかなる時も会社の迷うことのない指針です。
同時に、社員やお客様などステークホルダーを磁石のように惹きつける求心力でもあります。
カッコいい言葉である必要はありません。
社長の心の底から出た納得できる言葉であり、社員の肚に落ちる言葉であることが理想です。
自分たちで理念とビジョンを整え、存在価値を明確にする。
すると、会社にズシリと重い、ぶれない軸ができる。
その軸づくりをビジョン開発コンサルタントとして、お手伝いをしたいと考えています。
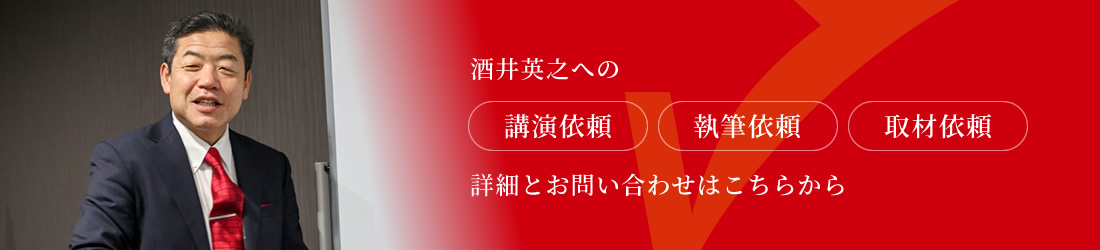
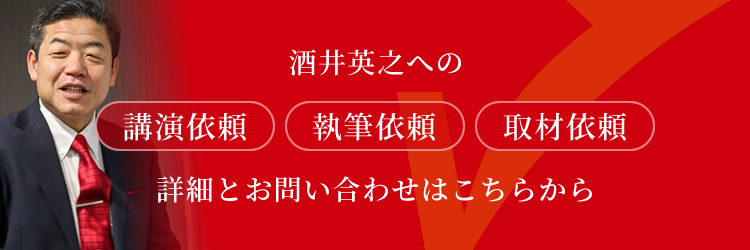
お知らせ&募集中のセミナー
NEWS & SEMINAR
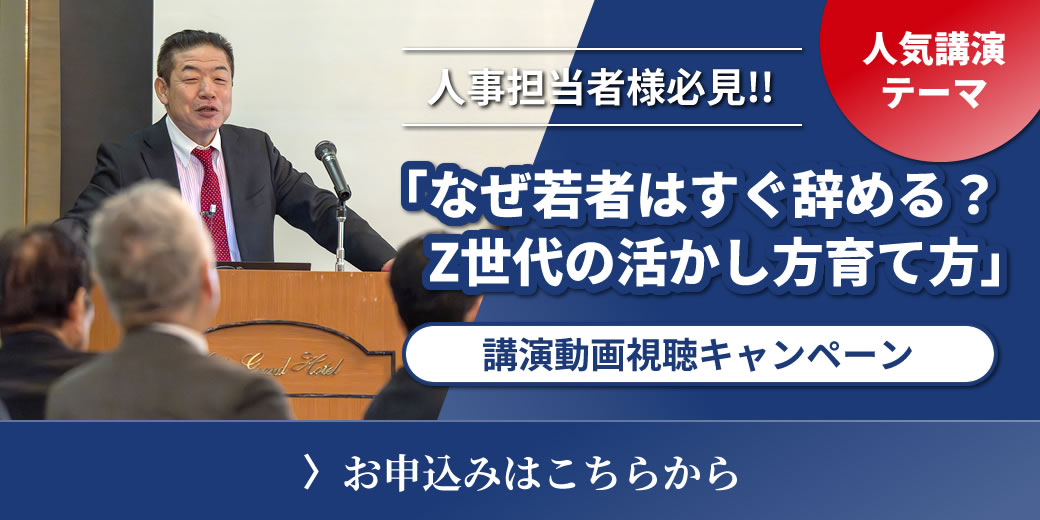
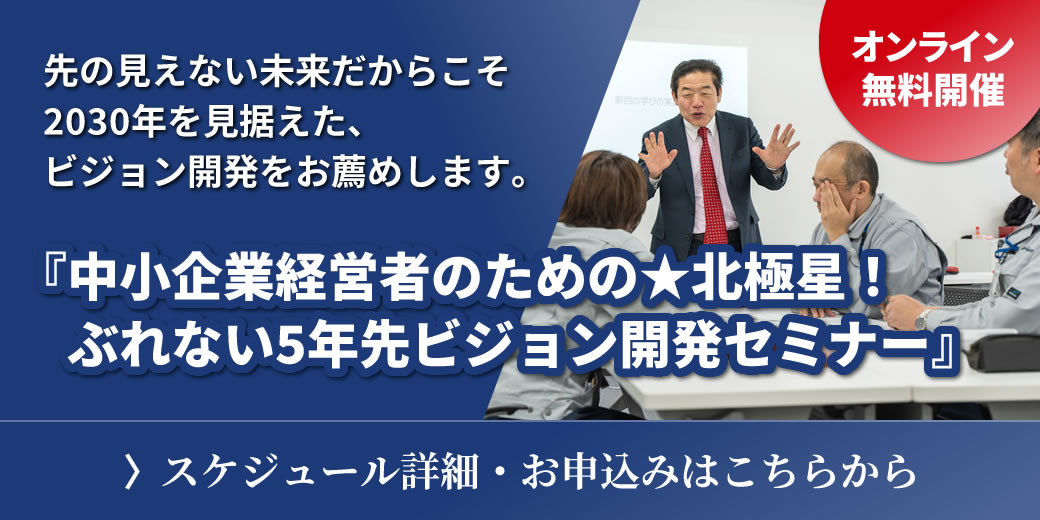

メルマガ
MAIL MAGAZINE
ビジネスマンを対象に週に一度配信しているメールマガジンです。
様々なチームの V 字回復事例や細部にわたる創意工夫を、時事ネタと連動させてお伝えしています。
また、V字研からのお知らせ、セミナー情報もお届けしています。
まずは内容を読んでみたいという方のために
バックナンバー
事業内容
BUSINESS DETAILS
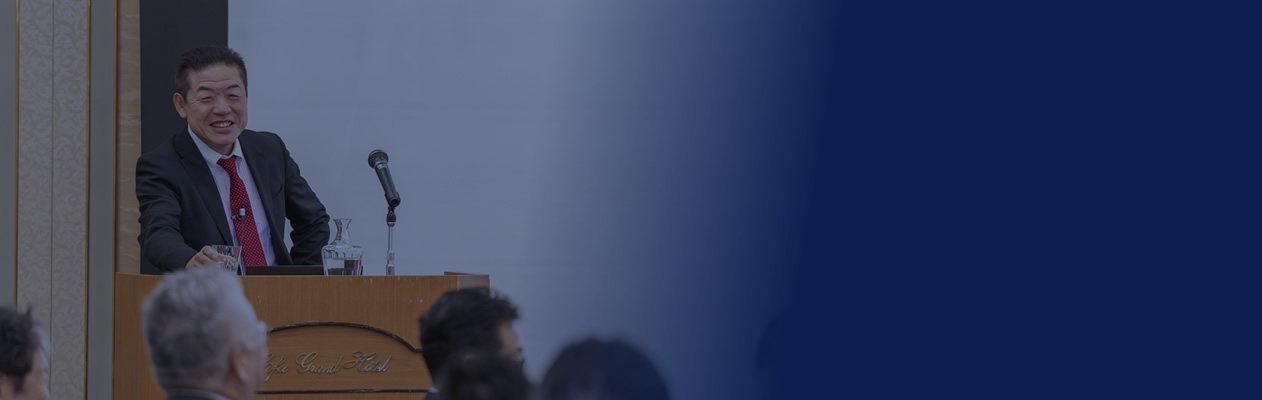

コンサルティング
CONSULTING

階層別・目的別社員研修
EMPLOYEE TRAINING



コンサルタント養成
CONSULTANT TRAINING COURSE

お客様の声
VOICE
-

株式会社フジワラ
代表取締役社長 松島雄一郎 様人間味があって愉快な人
-

株式会社大和工芸
代表取締役社長 市橋孝晃 様伴走し、正しい方向に導いてくれる人
-

株式会社蒲スプリング製作所
代表取締役社長 蒲好美 様現状をそのまま受け入れてくれる
-

トヨタL&F中部株式会社
取締役専務執行役員 井口晴夫 様手厚いフォローでやる気を引き出す
-

株式会社平出章商店
代表取締役社長 平出慎一郎 様同族経営こそ最強の事業継続の力
-

筒井工業株式会社
代表取締役社長 前島靖浩 様横同観という考え方は衝撃的でした
プロフィール
PROFILE

V字経営研究所
ビジョン開発コンサルタント
酒井英之
- 名古屋大学経済学部社会人大学院教員
- 経済産業省認定中小企業診断士
- FBAAファミリービジネスアドバイザー資格認定証保持者
1963年岐阜県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、ブラザー工業株式会社入社。考案したラベルライターがヒットし、同社がミシンから情報機器メーカーへV字回復する一翼を担う。1992年、戦略コンサルタントとして三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)へ。約400社を担当。 2014年「V字経営経験研究所」設立。ファミリービジネスを中心に携わり、2023年以降はZ世代に関する課題にも着手。独立以降500件の企業コンサルを行い、講座受講人数はのべ7万人。徹底した傾聴力と引き出し力にファンも多く、モットーは「人生送りバント」。
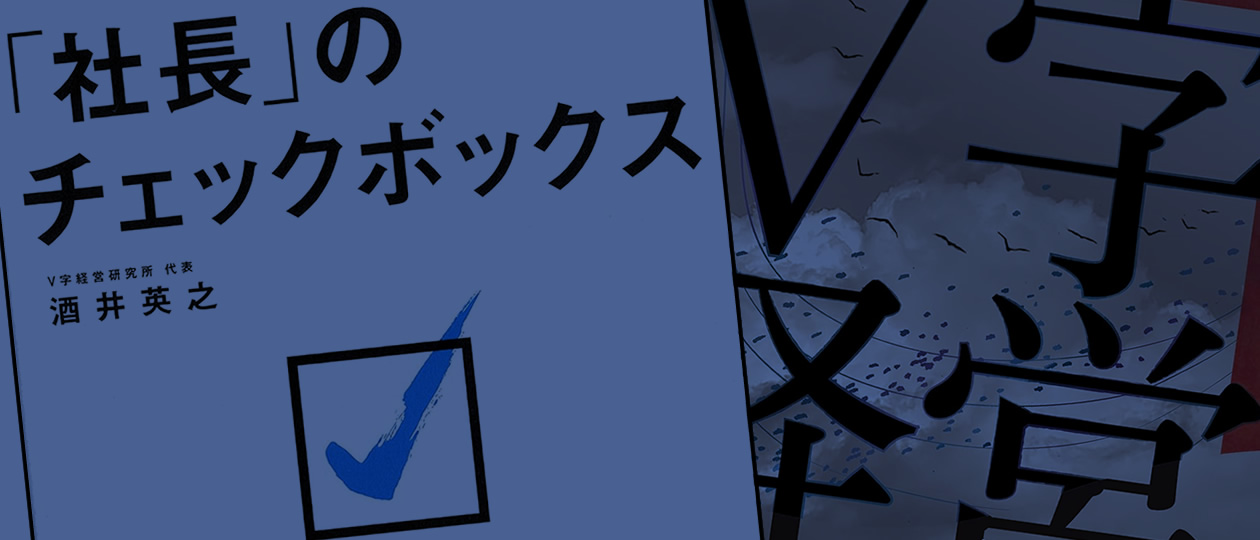
コラム・著書・
メディア実績