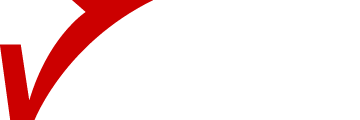水野孝一氏

水野孝一氏×酒井英之
「日本のどまつり」から
「世界のどまつり」へ
世界中のコミュニティを
元気にしたい
もはや、名古屋の真夏の風物詩と言っても過言ではない、「どまつり」こと、にっぽんど真ん中祭り。その代表を務める水野孝一さんは学生時代、札幌の中心地で大規模イベントを行う大学生の姿に影響を受け「ぜひ名古屋でもこんな影響を!」と大きな一歩を踏み出したそうです。「全員参加」が合言葉の「どまつり」は、その後行政やマスコミも巻き込み、今や国内外2万人以上の踊り手と、7,000人以上のボランティア、そして200万人以上が集う国内屈指の祭りに成長、2024年8月には26回目を迎えました。
そこで今回は、これまでの経緯や、挑戦したことでの発見、さらには今後、どうバトンタッチしていきたいかについて、水野さんに伺いました。
コロナ禍だからこそ見つかった
新しい「どまつり」の形
水野:
お久しぶりです。最後にお話ししたのがコロナ禍前でしたから久しぶりですね。
酒井:
相変わらずお元気そうですね。そしてまた「どまつり」の季節がやってきますね!

水野:
お陰様で、今年も無事に進んでいます。
先生には、仕事をはじめ生き方を教わり、特にコロナ禍を乗り越えられたのは先生のお陰です。2020年2月に「どまつり合宿」でお世話になったのが大きく、それがなければ開催できなかったかもしれません。
酒井:
それはよかったです。しかし私もコロナになった当初は「どまつり、正直どうするのかな?」と案じていました。
水野:
2月は8月の開催に向けたキックオフの時期なのですが、緊急事態宣言が出てしまい…。世界中をコロナが取り囲むようになり、「どまつり」も中止しなくてはダメなのかと。
祇園祭もそうですし、日本のお祭り自体が中止になったので。
酒井:
でもなぜか、「どまつり」だけは「中止にはしない!」という風向きになったそうですね。
水野:
ええ、「やらない」は選べなかった。なぜなら、もともと「どまつり」の役割は「地域の活性化」であり「人を集めてモノを動かす」ということで、この20年、ずっと信じてやってきたんですね。
コロナ禍になると人を集められないため、役割を果たせないから中止しよう、とも思ったんです。でも、「どまつり」の本来の役割はこういう時こそ、それぞれの地域やコミュニティで、役割を果たさなくてはと。結束力ってこういう時こそ発揮できるんじゃないかと思ったんです。
他の祭りと同じように「中止」を選んだら、大切な時に今後機能しなくなるのではないかと。

酒井:
「人を集めてモノを動かす」ことはできないけれど、「地域やコミュニティの動きを止めないことが大事」ということですね。
水野:
はい。
ですから強引と思いつつオンラインで開催しました。やり方や手順は全く想像できなかったのですが、それぞれの町や地域で短編映画を撮ったり、それをオンラインに集約して生配信したりすることで「どまつり」を開催する。
ところがこれを実行したところ、結局日本全国はもちろん、海外からもオンラインで「どまつり」に参加して下さいました。それが認められて、私たちが経済産業大臣賞を受賞したんです。
それがそのときのトロフィーです。日本に一人しかいないというレゴのプロビルダーが作ってくださいました。


酒井:
これは素敵ですね。ついつい写真を撮りたくなる
水野:
みんなの誇りです。非常時に結束して挑戦して勝ち得たもの。
「リアルではないから」と消極的に考えた面もありますが、積極的にコミュニティの動きを止めないという面にシフトチェンジし、「こういう時こそ、自分たちの理念に立ち返って活性化しよう!」という思いが実を結んだと思います。
酒井:
実際、コロナ禍の「どまつり」の動員などはどのような状況だったのですか?
水野:
お陰様で、思った以上だったんです。
これまでの20年間続けてきて、コロナ前の2019年にはチーム数約200、観客動員数は235万人だったのですが、2020年はオンラインにしたことで、なんとチーム数が2.8倍に。視聴者数も200万人オーバーとほとんど変わらず。
積極的に開催し、本来の役割を果たすことこそ「どまつり」には不可欠だと実感しました。


酒井:
それを受けた形になるのでしょうか、以前は、8月はリアル開催だけだったのに、今では11月に「テレどまつり」を開催しているそうですね。
水野:
11月はモリコロパークのリアルなステージで開催し、それぞれのチームの素材画面をバックに踊るという新しい演出ですね。雰囲気としては「オンラインのどまつりをリアルに開催」のような形です。
8月の「どまつり」はリアルに自分が踊り、リアルに観客が見るのですが、11月に関しては、映像で出場する分には制約がない。それこそ国内外どこからでも誰でも自由に参加できるので移動の制約とかで「出られない」というのがないんですよ。
酒井:
まさに多様性の祭典。垣根の低さが強みになりますよね。
水野:
そうなんですよね。これまで長くやってきた中で、短期間で大きく発展したのは、「多様性の受け入れ」にあると感じます。
「テレどまつり」は、「いつどこで練習」などの制限もないですし、誰もが各々の気持ちだけで参加できるんです。
酒井:
危機は危=ピンチと機=チャンスを掛け合わせた言葉ですが、コロナ禍という危機を、見事発展の機会にしましたね。
水野:
実は「どまつり合宿」の先生の講義で、仕事についての理念や価値について学び、「よしやるぞ!」となった直後にコロナ禍に。
中止の道もあったけれど、教わった「理念」を軸に考えることで新しい発想が生まれました。壁にぶつかったときに、「どうする?」ではなく「そもそも何のためにやっているのか?」「何がしたくてここまで来たのか?」に立ち返ることで活路が見えたのです。
酒井:
そうでしたか。理念の講義が役に立ったようで嬉しいです。「テレどまつり」もよく見させてもらいましたが、海外の方で10人くらいあの小規模のグループでも参加されていて「あ、こういう形でもいいのか」とか「従来はあまりなかったなあ」と感じました。
水野:
サイパンから日本の「どまつり」に出たいというチームがいらっしゃいましてね、でも40人という大人数で飛行機を使うと、どうしてもコストの面でネックになる。
でも制限がなければ自由に参加できるし、サイパンと日本がしっかり繋がって、お互い交流をする中で「日本に行ってみたいな」と言ってくれるようになるんです。
ですから、次のステージの時に交流に繋がるだろうなと、「どまつり」きっかけで新しい出会いが生まれると、嬉しい予測ができますね。
札幌で同世代の学生の活躍を見て、どまつり開催を決意
水野:
ある意味世界が狭く感じるようになったことで、次の役割は「名古屋って素晴らしい!」と気づいてくれた方に、足を運んでもらうことです。
何万人かに足を運んでもらい、名古屋での大交流がイメージできますし、歓迎したい。
酒井:
まさに、今いるこの、オープンな明るい空間!
「これが名古屋ですよ」という。栄のど真ん中という立地もいいですもんね。
映えポイントもたくさんあります(笑)。

水野:
こちらは「テレどまつり」のスタジオでもあり、四半世紀なんとかやってこられて、25年間のいろいろなことが詰まっています。
実はスタジオは「徹子の部屋」をイメージしているのですが、ここには1999年に出した企画書が飾ってあります。
この企画書に思いをしたためて、とあるプランナーに見ていただいたのですが「思いだけでは地域は活性しない」とアドバイスをいただき…。それで、企画書には「思い」は載せず、「日本のど真ん中から元気を発信」というフレーズとともに、理屈だけの企画書が出来上がったのです。
ところが、この企画書をもとにプレゼンしたのですが、誰の共感も得られなくて。
結局、自分たちの言葉を武器に、なぜこのような取り組みを始めたいと思ったのかという「原体験」を語ることで、祭りの支援者が集まりはじめました。
酒井:
そうした紆余曲折があり、今に繋がるんですね。
ところでそもそも、「どまつり」って名古屋の学生たちの挑戦から始まったんですよね?
水野:
当時、北海道の大学生らからの誘いで、彼らが企画運営する祭りに66人の名古屋の大学生が参加したことがきっかけです。道路を止めて、大音響の中で生き生きと踊る老若男女に混じり、私たちも踊りに参加しました。
踊りに関心が無い私でも、踊らずにはいられない雰囲気に包まれ、いや完全に飲まれていたかもしれません。この巨大なフェスの仕掛け人が、同世代の大学生であることに驚きと大きな嫉妬心を抱きました。しかし、この驚きや嫉妬心が私自身の原体験となり、後々に繋がったと思います。
すぐに企画書を作りましたが、今見ると、正直共感は生まれないかなと感じましたね。
酒井:
僕も拝見した記憶があるのですが、そんな出来でしたかね?
水野:
酒井先生がおっしゃった「共感」という視点で考えると、本当の気持ちが乗ってないんですよね。なんというか弱い。
それが99年に形になったのは、水谷先生のお陰です。
実は先生には「なんでやりたいの、やめときなさい」って止められたんです。
(名古屋大学客員教授 水谷先生 https://vjiken.com/conversation/mizutani)
でも理屈ではなく、やりたいという思いが強かった。本音は「北海道に負けたくない」だったのだけれど、「原体験をもとに自分の思いを言葉にし、伝えることが大切だ」とその時に痛感しました。
酒井:
では原体験を語ったんですか?
水野:
札幌の街中で踊った時、そもそも踊りには興味がなく恥ずかしかったのに、祭りの空間では踊らないわけにいかず…でもそれが楽しかったんです。
さらに、すごく大きなことを、同世代の子たちが作っている。道路を止めて、たくさんの人を集めて、もちろん資金も調達して…そのすごさに圧倒されると同時に憧れました。
ご存知のように、札幌の中心地と栄って街並みがそっくりなので、名古屋でも必ずできると思いました。
その時「TDL(東京ディズニーランド)イマジネーション研究所」から得た「想像できることは実現できる」というフレーズに出会ったのもあったかもしれません。
酒井:
「想像できることは実現できる」。いい言葉ですよね。今をときめく大谷選手も、想像できたから今があると言われていますし。
結局、水谷先生にはどう伝えたんですか?
水野:
「名古屋で一番の街を作りたいんだ」と言いましたが「やめなさい」と。
それでも、北海道の学生にはできて、私たちにできないと思えなかったんです。先生が大変お忙しい時で、伝えるのに5分しかなく、書面もなかったことを覚えています。
その後、改めて大学院で水谷先生から2年間学び、振り返ってみると、「共感や思いを言葉にする連続」だったなと思います。
とはいえ、25年の中では借金が重なりお祭りをやめようと思った時もありました。
そんなとき、ある8歳の女の子から「いつか私も『どまつり』に参加することが楽しみ」って言われたんです。実は彼女は白血病を患っていて、治療のため入院していたのですが、「どまつりで踊ること」が、彼女の生きる希望になっていたのです。
それを知って、自分たちは期待されている、頑張りたい、応えたいと思いが沸いてきて、やめるわけにはいきませんでした。
こうして25年間、周りのたくさんの言葉に勇気づけられて、続けてこれたのだと感じます。

酒井:
水谷先生の言葉は、人を動かしますよね。
私の話で恐縮ですが「酒井さんは何がしたいの?」って尋ねられた時に「神輿に乗る人、担ぐ人がいるけれど、私はそのわらじを作りたい」って言ったんです。神輿にのる社長、担ぐ社員がいるけれど、その方たちが元気に跳ねられるようなわらじを作りたい。つまり働きやすい環境を整えたいということを伝えました。
この言葉はつかこうへいさんの小説『龍馬伝』に出てくるのですが、私はこれがコンサルタントの仕事だと思っていたのです。
世の中のコンサルタントの中には、全国区単位で有名になることを目標にしたり、著書が100万部突破…なんて派手なことを夢見る方もいます。自分が主役、という発想ですね。
が、私はそうじゃなくて、目の前のお客様のために一生懸命やる。それが一番楽しくてやりがいがあると思っています。
そしたら、先生にいたく感心されて。それが自分にとっての勇気になりました。
水野:
いい言葉ですね!先生、ぜひまたセミナーをやってください!
酒井:
ぜひぜひ喜んで(笑)。
先程セミナーの話題になりましたが、「どまつり合宿」も継続されていますよね?
「どまつり合宿」で、チームワークや学びを培う
水野:
はい、前述のように2020年2月には先生にお世話になりました。
やはりコロナ禍が明けて、あの時とは状況も異なり、それでいてワンクッションありましたから、いつかまた先生に教えを請いたいですね。
酒井:
そうそう、「どまつり」に参加している400人が水明館に1泊2日で泊まって、グループ単位でディスカッションしましたよね。
僕がチームを経営に置き換えて、「理念は目標とは違うよ。理念とは、目標とは」をお伝えしました。
水野:
チームの中には純粋に踊りたい人もいれば、絶対に優勝したい人がいます。同じチームで目標が混在していると、チームが分離したり誰かが犠牲になったりすることがあります。
そんなチームがギスギスしないためには、「何のために皆で踊るのか」というチームの理念を言語化し、そこに焦点を当てて、そこから自分たちのあるべき姿を考える。すると、自ずと答えが見つかるというセッションでした。
酒井:
コロナ禍の直前に、理念について考える機会があったのは、よいタイミングだったかもしれませんね。
水野:
気付きが多かったですし、スタッフ一同結束してコロナ禍に立ち向かえました。
コロナ禍を経て今思うのは、集客や参加チームの数はどうでもよくて、私たちの本当の役割は何なんだとか、それをどう果たすのか、もともとの存在価値や意義に思いを馳せるのが一番だと思ったんです。
そして、根本的には「チームとスタッフの心がひとつになれたら最強!」だと。
コロナ禍は、その大切なきっかけになりましたね。
実行委員会の主体はあくまでも学生。
その中で「学び」を見つけて欲しい。
酒井:
改めて、今はどんな運営をされているのですか?
水野:
現在も「ワンチーム」を基本にし、実行委員会として運営しているのは学生です。学生を主体にしているのは、25年間変わりませんね。活動を初めて、毎年1本のバトンを受け継ぎながら続けています。
やはり「学生が実行委員となって祭を作る」というのが大前提。
当日は8~900人の学生が参加して、それとは別に町内会や行政のボランティアさんが、概ね6,000人くらい参加してくださいます。
わらじを作る役割は、私たち古参の6人。神輿を担ぐ皆さんのためにせっせとわらじを編みますが、もしかしたら、学生たちにも体験をさせてあげるのがいいのかなと思います。
酒井:
具体的には、どんな体験ですか?
水野:
やはり成功体験ばかりではなく、失敗も経験して欲しい。
思いを形にするのって、伝わらなくて、上手くいかないことの繰り返しだから、必ず苦労します。が、苦労こそ若い人の財産になると思うんです。
例えばサークル活動やアルバイト、それこそ学校や日常でも得られることはたくさんあるけれど、だいたいが成功体験。
でもそうじゃなくて、人生の中で「願っても叶わない」とか「伝わらない」ということにぶつかり続けるというか…これは僕自身がそうだったのですが、親心というんでしょうかね。神輿を担ぐとか上に乗る人ではなく、わらじを作ることを体験して欲しいとどこかで思っています。
酒井:
警察の許可ひとつとっても、大変ですもんね。

水野:
ええ、警察って理念では動いてくれないので…
最初の頃なんて、「どまつり」自体が伝わらないから、一生懸命説明してようやく「青森のねぶた祭が好きなんだよね~。ああいう感じですか…」なんて言っくれる警官がいて、それでやっと伝わったり。
酒井:
初めてのものは、伝わらない。それを骨身で感じることは、学生にはとても有益ですね。
水野:
「どまつり」が成長する過程では、各地域の皆さんからダンス以外のものを期待されます。
キャラバン隊もそうですが、1年半で、市町村全部をまわりました。総踊りへの参加や、「どまつりで踊るチームを作ろう」という運動をしてきましたね。
でも地方に行けば行くほど、新しい目というか、いろいろな好奇の目で見られて…それが例えば「うちの町の子どもたちのためにも取り組んで欲しい」とか「うちにはこんな特産があるんです」とか「出会いが欲しい」とか。
いろんな、深刻なニーズがあり、それに応えるためのツールとして「どまつり」に期待が集まるんですよね。
当初は「学生たちのコンテスト・祭典」という色が強かったのですが、市町村をまわる中で、出会いがあったり、小さい子から手紙をいただいたり。だんだん市町村単位で期待されるから、それに応えていきたいと思うようになりました。
酒井:
最初の頃と比べると、認知度が上がり、期待値も要望も大きく広がった。
水野:
はい。創業期は「札幌に負けたくない」という自己実現欲求が中心でしたが、市町村をまわっていろいろな期待の声を伺ってから「応えたい」という使命感というフェーズに変わってきましたね。創業期との大きな違いはまさにここです。
ですから改めて1999年の企画書を見て「違うな」と思いました。今は四半世紀が過ぎて、50年構想の時期に入っていると思います。
やはり理念って、人に伝えて共感を生まなくてはいけないと思うんですよね。
25年経って、先生の講義を受けて、改めて理念を考えてそれぞれの思うことを言葉にしたように感じます。
酒井:
コミュニティ形成も、その中のひとつですよね。
水野:
市町村のニーズとして、応えたいと思いましたね。だからこそコロナ禍で、私たちが20年以上培ってきたコミュニティが結束力を生み、「テレどまつり」ができたのだと思います。
本当に、先生のお陰です。
酒井:
いえいえ、水野さんはじめ実行委員会の皆さんの頑張りだと思いますよ。
地域の期待って、形が変わってきていますよね。本当に町内会や子ども会が消えていってお祭りもなくなって…学校でもPTAや地域活動が減っています。
そんな中で、地域が一つになれる「どまつり」の役目は益々大きくなっていきそうですね。
「どまつり」を軸に気づく、
地方の課題や人との繋がり
水野:
私はPTAさんとも関わっていますが、時代は変わるのに、組織が変わっていかないのは残念ですよね。時代が変われば仕組みが変わるのが当たり前なのに、変えられないというか…。
もちろん理念があってのことだけれど、柔軟にフレキシブルに、本来の役割を遂げつつ、時代とともに組織も変化していかないといけないなと思います。
コロナ禍に運動会を中止する学校が相次ぎましたが、オンラインを使うとか、やり方はあったはずなんです。そうした代替案もなく「3蜜禁止=運動会中止」という結論になってしまうのは、根源にある理念を見失っている気がするんです。
酒井:
確かに。理念や使命感あれば、やり方を変えても別の方法を考えることはできますから。
PTAももともとは理念があったはずなのに、やり方だけがそのまま残り、理念がどこかに行ってしまったんでしょうね。何となく、従来のやり方を続けるのが正しいという風潮になり、「理念を貫くためにやり方を変える」という発想はないんですよね。
水野:
実はプライベートで、2020年に小学校のPTA会長をやっていました。コロナ禍でいろいろな活動が中止になりそうな時に、子ども達の学ぶ環境がどんどん変わってきているので、今こそ従来の形に捉われずに役割を果たす時だと思ったんです。
そこで、給食の試食会と銘打って、調理室から生配信という取り組みをしてみました。
もう保護者さんも巻き込んで。
私がツールを持っていたこともありますが、大人の方に試食をしてもらって「旨い!」なんて言ってもらったり。
あとは授業の様子の生配信もしました。機材を全部ワゴンに載せて、教室をひとつひとつまわってね。もちろん議論もありましたが、すごく面白かった。コロナ禍が明けても「あれよかったよね」っていう話にもなりました。
戻すことに抵抗がないなら、そのまま続けてやればいいですよね。「どまつり」もそうだし、PTAも。
これから、変化や変革が求められていると思うし、それにあたり軸や根幹になるのが、やっぱり酒井先生が言われる「理念」だと思います。

酒井:
今お話を伺っていて、やっぱり理念というぶれない軸があるから変われるんだなと思いました。
逆に、変われなくなっちゃうのは「やり方」にこだわるから。
もし給食の試食の生中継が当たり前になったら、新しい発想は出てこなくなります。「どまつり」も「テレどまつり」が成功したけれど、そのやり方に固執したらそこで止まってしまいます。
が、理念に立ち返ってさらに多様性を追究したところ、モリコロパークでリアルで踊る人と、そのバックには世界各国で踊っている人の映像を流す…と新しい姿ができる。
理念がしっかりしていれば、環境やニーズの変化に対応して出来ることが増えて、柔軟に取り入れられるんでしょうね。
それがないとやり方に固執し「時代が変わっても仕組みは変わらない」という結果になる。組織も同じかもしれません。
水野:
こういうことって、教わって伝わるものでもないし、逆に学生たちに教えるものでもないし…物語に共感し、気持ちを共有し、理念を自分ごとのように語れるようになると、面白いなと思いますね。
「どまつり」も25年が経ち、やはり僕の役目も終わろうとしていると感じます。
ギアチェンジの時というか…次の世代が彼らなりに役割を自覚しながら、祭りを作って欲しいと思います。
いつまでも創業期のギアでは、次のステージに行けないので、「場」を共有することを意識しています。
酒井:
「場」ですか。それは具体的にどんな存在ですか?
水野:
まあ、どうでもいいようなやり取りをしながら、なるべく共有しながら、同じような感覚が伝播していく状態でしょうか…。
そうした価値観や感覚みたいなのを意識しながら、座学ではなく自然と伝えたい。
ですから、そろそろ、酒井先生にも教わった「理念・物語」型のギアチェンジを実践する時なのかなと。
酒井:
それは、いわゆる「世代交代」のことでしょうか。
水野:
そうですね。確実に必要だと思っています。
もし1人で難しいなら、2人、3人にしたり、もしくはさまざまな世代で幾重にも重なるコミュニティにしたり…といろいろ考えますね。
世代交代って、一般的にはうまくいかないと言われますが、私は憧れや楽しみを持っています。
酒井:
確かにうまくいかないと言われがちですが…水野さんの場合はメンバーに学生さんが多いので、企業さんの交替とは違うし、時代とともにアップデートできるのではないでしょうか。
水野:
やはり私たちの業界のプロジェクトとして、それぞれがそれぞれの立場で物語を語って欲しいと思うんですよね。いつまでも「水野のストーリー」ではなく、それぞれの物語として表現して欲しいです。
酒井:
そういう面白さはありますね。企業でいえば「うちの息子ならどうするかな?」のような。
これは持論ですが、二代目って先代の気持ちを一番語れないといけないなと。
そして社内の誰よりも理念に共感し、理念が好きでないといけない。
水野:
前述の、水谷先生の大学院の授業でも、それがとても印象に残っています。
「事業の内容を覚えているってどういうことだろう」から始まり、人間の絵を板書されて「この、魂の部分を語れる人間になりなさい」と。
酒井:
次の世代は、思いは受け継ぐけれど、やり方はその時代を生きる人だけのやり方があると思います。
逆にそれがいい味を出すわけで、「やり方を変えたら許さない!」というより、「新しいやり方を楽しみにする先代であれ」と思います。
水野:
私は変わり続けることに価値を見出してきたので、これからどんな価値に出会えるのか、とても楽しみなんです。
形を変えながらも学生を中心にし、
新たな未来へ。
酒井:
「どまつり」の歴史は、名古屋の歴史そのままですよね。
セントレアのオープン、万博の開催…すごくリンクしているので、それを見ているだけで、この25年で名古屋で何が起こったかが一目瞭然。
そういえば、2025年の大阪万博にも出られるそうですね。
水野:
はい。8月の夏休み真っ盛りの土日に予定しています。
「にっぽんのどまつり」から「世界のどまつり」に変わろうと思って…コミュニティを大切にしたいなと。日本ではなくて名古屋だけれど、世界中の方々とのコミュニティを元気し、世界が心ひとつにできるような「世界どまんなか祭り」にしたいと思います。
酒井:
人類共有の文化という面で考えると、自ずと「世界」というワードが入ってきますね。
水野:
韓国の街中で日本の音楽を大音量で流した時、警察が来たという話があります。
でも「どまつり」をちょっと披露したら、みんな楽しそうに参加してくれて。
「どまつりって、日本だけの表現ではなくて、世界での誰もが参加できるんだ!」って実感したんですよ。
それを期に、ソウルや釜山の大学にもプレゼンして、チームができて…今もその子たちとの交流が続いているんです。政府としては反対したそうなのですが、学生たちが「私たちの世代で今から新しい地盤を作っていくから」と政府を説得してくれて。
結果、日本に来てくれました。嬉しかったですね。
酒井:
まさに「理念」に共感してくれたというわけですね。
水野:
人類共有の世界文化が「どまつり」のベース。大阪万博もありますし、こういう時代だからこそ世界がひとつになる価値観が必要だと思います。
ぜひ大阪万博にお越しください。
酒井:
愛知万博も9回ほど行きましたからね、大阪万博も今はいろいろ言われていますが、始まったら殺到すると思います。
水野:
リアル開催のほか、バーチャル大阪万博みたいな組み合わせるんですよ。総踊りにリアルに参加するのも楽しいですが、「テレどまつり」の実績もあるので、オンラインで一緒に盛り上がれる方法を考えています。
酒井:
別会場では、フィルムコンサートなどもするそうですね。
水野:
世界中の民族楽器で音楽を作るような試みらしく、「We are the World」みたいな感じでしょうかね。
一緒に歌ったり踊ったりするのは楽しいと思いますよ。
暑さ対策も評価されるよう頑張ると思いますので、ぜひ来てください。お招きします。
酒井:
ありがとうございます。とても楽しみにしています。これからの展望は?
水野:
やはり我々は、リアルなお祭り、心躍る祭り、非日常の賑やかさを持つ祭り…という印象を持っていると自負していて、旅行先としてみんなが「どまつり」を選んでくれるような、魅力たっぷりのものにしていきたいですね。
テレビ塔の周りも雰囲気が変わり、オアシスの景色と相まって、人気が集まっています。
いわば、エッフェル塔に模した感じとして、世界に売り出していけたら。
酒井:
中日ビルも新装オープンしましたし、最近栄は元気がありませんが、いいきっかけになっていますよね。
水野:
そうそう、久屋大通公園の池の水を抜いて、そこをパレードコースにして踊るんですよ。




酒井:
それはすごい試みですね。こういうのって地元にいると気づかない価値なので、「どまつり」の舞台になることで、今の人たちやもっと多くの人に知って欲しいですね。本当にいい景色だと思いますから。
水野:
8月の「どまつり」、そして11月の「テレどまつり」。モリコロパークとオンラインで繋ぐ、世界最大級のオンラインイベントです。
酒井:
まさにオリンピッククラスの規模ですね。万博も含め、これからの大躍進を心から期待しています。
プロフィール
水野 孝一(みずの こういち)
にほんど真ん中祭り 創設者、(公財)にっぽんど真ん中祭り文化財団 専務理事
1976年岐阜県生まれ。1994年中京大学商学部に入学後、札幌にてYOSAKOIソーラン祭りに参加。「にっぽんど真ん中祭り」の開催を構想し、1999年に「にっぽんど真ん中祭り実行委員会」を結成、現在に至るまで執行責任者を務める。同年、中京大学卒業。
2001年「日本ど真ん中祭り普及振興会」事務局長に就任。同年、名古屋大学大学院経済学研究科修了。
2012年、どまつりが公益財団法人として認定される。2022年には、JACEイベントアワード最優秀賞、日本イベント大賞(経済産業大臣賞)受賞。
3児の父として、名古屋市立小学校のPTA会長や地元学区小中学校PTA協議会会長も務める。
2024年、名古屋市教育員会 委員に就任。
https://www.domatsuri.com/