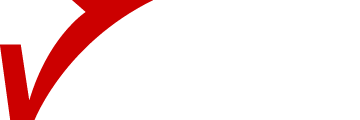富塚祐子氏

富塚祐子氏×酒井英之
毎週届けるメルマガに
京セラフィロソフィを凝縮
不動産関連事業を中心に、海外進出のサポートや英会話教室などの事業を手がける、「アブリールス株式会社」代表取締役社長の富塚祐子さん。かつては日本の企業の年功序列・欧米至上主義に疑問を持ち、諸外国で学びを重ねたそうです。しかし30年で学んだことは、欧米の価値観にも日本の価値観にもそれぞれに良さがあるということ。現在は経営の神様、稲盛和夫氏の哲学に感銘を受け「京セラフィロソフィ」を1人でも多くの方に伝えたいと、毎週メルマガにて「利他のこころ」「日本人のおもいやり」といった、稲盛氏の考えを発信されています。
今回は世界を見たからこそわかる日本の素晴らしさ、さらには最近極めている合気道や着物、華道について、その面白さとお仕事との共通点を伺いました。
毎週届くメルマガに
京セラフィロソフィが凝縮
酒井:
お久しぶりです。リアルでお会いするのは、コロナ前に日本ファミリービジネスアドバイザー協会(FBAA)の視察会でイタリアにご一緒して以来ですね。その時先生はコーディネーター兼通訳で活躍されて、「雲の上の人」という印象でした。大変多くの学びを頂きました。心から感謝しています。
富塚:
そうですね。イタリアの視察会は2019年でしたから、もう5年も前ですね。あのツアーは、フェラガモやダミアーニなど、イタリアの有名なファミリービジネス企業を見て回りました。刺激が一杯でしたね。
酒井:
そうです。その印象が今でも鮮明なのと、先生からは毎週メルマガで「京セラフィロソフィ」を届けてもらっているので、毎週お会いしているような気がしています。
このメルマガ、毎週毎週欠かさず続けていらっしゃいますが、まずは、そのモチベーションはどこから来るのかをお伺いしたいです。
富塚:
当初は「自分がどんな人か」ということを伝えたいのが第一の目的でした。が、稲盛さんがいつもおっしゃっている「心を磨き続ける」ということを、日々自分がやっていきたいというのが、モチベーションの一番のベースになっています。

生きていると、ついうぬぼれたり、人を見下したり「ああすればよかった」と後悔や反省をします。これをしっかり考えてアウトプットすることで、自分の考えがまとまるんです。
ですから自分の心を磨くための「反省と記録」のような感じでメルマガを書いています。
また「誰かが読んでくださるかも」「誰かのお役に立つことができるかも」という気持ちもあるので、お仕事をするパートナーさんや提携会社さんにも読んでもらっています。
酒井:
それだけでもすごいのに、英語版も書いていらっしゃるんですよね。
富塚:
はい、私は最初日本の企業に12年いて、勤務地は名古屋でした。時代的に「海外は進んでいて日本は遅れている」というのを感じ、海外に行きたいと思うようになったんです。
そこで海外に渡りMBAを履修したのですが、実際に海外で学んでみると、日本のものが全部ダメなわけではないと思ったんです。
酒井:
日本にもいいところがあることを、海外で学ぶことや外資系企業で働くことで実感されたのですね。
富塚:
「無理に外国の真似をしなくてもよい」ことに、改めて気づきました。
例えば、ビジネスや会社のやり方について、海外のMBAを学ばないと通用しないと思っていたけれど違いました。欧米それぞれ外資系の会社で働いた時には、マネジメントに違和感もありました。特に、ビジネスの目的が結局「お金だけ」というところに帰結してしまうところが残念でした。
酒井:
日本は島国ですし、国外の意見が強く正しいように感じたけれど、行ってみたら違った。
富塚:
この先の人生で「海外で働いても私の望む目的と合わないんじゃないのかな」と感じ始めました。
そんな時、稲盛さんの考えと出会い「これこそが、人間として正しい生き方だ」と思うようになったんです。
そして、正しいと思ったやり方で成果を出していらっしゃる。お一人で京セラを立ち上げ成功させ、破綻していたJALを短期間でV字回復させた。すごく価値がある、まさに日本人が学ぶべき考え方だと思いましたね。
もちろん華やかに成功されている方に憧れるのもいいと思います。が、私は稲盛さんの考え方こそサスティナブルであり、人間としても素晴らしく、企業も個人も幸せにすると思いました。「働き方とかやり方」であるのと同時に、人としてどうあるべきかを説いた「あり方」と言いましょうか。
ですから草の根運動ですが、自分が「世界で最強だと思うこの哲学」を発信していきたいんです。

酒井:
すごい決意ですね。メルマガを書かれるにあたり、具体的には稲盛さんのどんなコンテンツを活用されていますか?
富塚:
私が所属していた盛和塾は、今は解散しています。ですが、個人的に車の運転中にデジタルコンテンツを聞いています。著書である『京セラフィロソフィ』については、日々話して感想を仕事上のパートナーさんに書いてもらったりしていますね。
世界中の方に発信する中で、
お国柄で伝わり方が異なるのが悩み
酒井:
このメルマガは英語版もあるんですよね。
富塚:
『京セラフィロソフィ』は日本人の経営哲学だと思います。ですので、海外の方に知って欲しいんです。ですから名刺交換した方には、日本語と英語版を半ば強制的に配信しています(笑)。
メルマガって地味ですが、反応が来ると嬉しい。稲盛さんのお話は海外の方からも「素晴らしい」という感想を伺います。
メルマガでは、医師の中村哲先生のお話もよくします。世界平和を説くのなら、海外に自分の銅像を建てるのではなく、地元に求められていることを地味に地道にやることが大切だと思うんですよね。

酒井:
地味なことを地道にやることはとても大切なことですね。ただ、時々サボたくなるのが人間です。私は、メルマガの配信ときどき休んでしまいますが、先生は毎週日曜日の朝7時に必ず配信しておられる。地味なことを決まった日に、決まった時刻に何年も続けていることは凄いことです。
富塚:
ありがとうございます。
酒井:
また、内容も素晴らしいと思います。とにかくまとめ方が素晴らしい。
まず、『京セラフィロソフィ』等から引用した稲盛さんの言葉があって、それを身近な出来事に置き換えて、必ず3つの切り口で解説するという構成で、「言葉→置き換え→解説」という流れがとてもわかりやすい。
特に24年の12月22日に配信された「アメーバの罠-フィロソフィ『仲間のために尽くす』」は、お客様ともよく議論しているテーマです。会社の中の特定の課や営業所のような小さな組織(アメーバ)が好業績を上げた場合、他の組織に比べて賞与を多く支払うべきか否かという点です。
https://abrils.opal.ne.jp/philosophy/the-trap-of-amoeba-system-philosophy-devote-yourself-for-your-colleagues/
稲盛さんは『京セラフィロソフィ』の「好業績に報いる方法として、名誉だけを与えるという形をとってきました」(P86)と述べています。それを当社に置き換えて、それでいいのかどうかについて話し合うのです。
富塚:
24年の12月に行われた盛和塾の世界大会でもその話題が出ました。参加していたのはブラジルやハワイやロス、もちろん日本人も多かったですが、不思議なことに中国の方は「中国」と団体でまとめて来られるんですよね。中国の方は1000人単位で来場されて盛り上がっているし、こちらも受け入れるんですけれど、私たちはそれを淡々と見ています。
思うに、中国の方にとってのアメーバ理論は、人をやる気にさせるにはいいけれど、稲盛さんの指す「仲間のため」「利他」という考え方がお国柄として浸透しないと思うんですよ。
だから業績が上がっても長続きしない。本当に上手くいくためには、フィロソフィとの両輪が大事。稲盛さんもその部分にはエネルギーを割いていたと思います。
酒井:
稲盛さんは「ご自身も周りも顔が赤くなるまで話した」「エネルギーが転移するまで伝えた」という逸話もありますよね。
富塚:
稲盛さんの部下だった方は、「こちらが少しでもいぶかしげだと稲盛さんは『お前はまだわかっていない』と相手の顔色が上気してくるまで話した」というエピソードがあります。さらに先ほどの成果主義については、海外の方には「自分が業績をあげたのに、それがなぜ報酬として表われないのか」が理解できないケースが多いです。
表現はむずかしいですが、これこそが「踏み絵」ですね。業績と報酬をどのように考えるか、どのような仕組みを選択するかによって、京セラフィロソフィがその会社にとって上っ面だけなのか、世界最強の経営哲学に変わるかが大きく違ってくるほど大きな問題だと思います。
京セラフィロソフィのベースにある
「利他の心」は生き物の本能
富塚:
アメーバ経営という小集団活動では、フィロソフィという「心」や「考え方・生き方」がすごく大事なんですよね。
少し厳しい面もあるので、「フィロソフィ」を導入する側も現場から「拒否されないか」「パワハラなんて言われないだろうか」と怖がって導入しないケースもあるんです。でもやっぱりやった方がいい。

酒井:
本当に大いにやるべきだと僕も思います。ただ前述のように、アメーバ経営の活動評価で、賞賛は得られても金銭的な報酬がないのは、難しいところでしょうね。
「そうだよね」になるか「おかしくない?」になるか。頑張った人が見返りがないと感じ、会社を辞めてしまうケースもありますし。
富塚:
極端に言えば、日本以外はそうでしょうね。「なぜ報酬として評価されないのだ?」と。
でも問いたいんですよ。「頑張ったのは果たしてあなたたちだけなんですか?」って。そう考えると、会社のブランドがあったり、先輩の布石のお陰だったり、他のチームの頑張りだったり、絶対に個人1人の力ではないんですよ。
酒井:
たまたまその時だけかもしれないし、結果に対して賞与が出ても、下がった時には出ないから、そうなると腐って辞める人も出てくるかもしれない。
富塚:
そうです。だからこそやっぱり「人のために頑張るのが、人として一番尊い行動である」ということを強く伝えたいんです。これが宇宙の法則であれば、実行している京セラが成功したのは正しいという証明になります。
例えば生物の世界では、全体の種を生かすために、個が存在するのです。人間も本来はそうあるのですが、同時に、人間は利己的な面もあります。なので、この利己心が全面に出てしまうのです。
酒井:
確かに、人間以外は種の保存のために、個が犠牲になりますね。ケニアでも草食動物が群れで移動するときに、ケガをした個や子供が群れから遅れてそれを肉食動物が捕まえて食べるわけですが、その一頭が犠牲になることで群れ全体が救われています。
弊社の社名の由来にもなっている「鳥のV字編隊」でも、老いた鳥が自分から進んで猛禽類に一番狙われる外側を飛びます。それは自分が猛禽類に襲われることで群れを守るためです。
富塚:
先生のご趣味である釣りでも、鮭の両親は、稚魚を生きさせるために自らが死を選ぶそうです。自分が死ぬことで、子供たちはエサを取りやすくなるからです。動物の世界では、生殖の機能がないモノは餓死し、その分を他の動物にまわす仕組みになっているので、生き物の一部である人間でも、やはり美しいのは「仲間に尽くす」ことだと思います。
酒井:
なるほど、人が「人のため」「利他の心」で動くのは人間の生き物としての本能なのですね。
富塚:
結局「循環」ということを稲盛さんは言われているのだと思います。
だからそこに、自分のためだけの金銭での報酬の話を持ってくるのは、少し違うというか。
実際は、小集団も時間あたりの生産性で測ったり、全体をベースアップしていくやり方もあるので、考え方次第といえます。
京セラの場合は従業員の持ち株制度も素晴らしいので特殊ですが、特定の部署だけが金銭で報酬をうけるのはやはりおかしいですからね。
日本の不動産制度を世界に伝える伝道師に!

酒井:
ちなみに先生の目標は?
富塚:
「日本が誇る優れた不動産の仕組みを、海外に広げる伝道師になる」です。
その目標に対して、今日1日何を目指し、何を考えて働くのか意識し、1日の終わりには達成できていたかどうかを顧みています。
富塚:
稲盛さんの言葉は、例えば「嘘をつかない」とか、当たり前のことが淡々と綴られているので、余計に響くんですよ。
仕事をすると本音と建て前があったりするのですが、やはり稲盛さんがおっしゃるように嘘がない方が働きやすい。それは日本企業でも外資系でも同じではないでしょうか。
酒井:
日本も外資も、株主と一部の役員のために働くという傾向がありますが、それは寂しいですよね。会ったこともない方のために働いているというのは。
富塚:
アメリカも日本もそこを目指しているのでしょうが、稲盛さんは大反対されています。
会社はまず全従業員のためにあり、そこから余剰が出たものを出資者の方に配当するという流れが理想ですから。
不動産の買い方、活用法は
日本と世界でこんなに違う
酒井:
ここからは、富塚先生のご専門である不動産業界についてお訊ねしたいのですが、この業界って、まだまだ日本では歩合制を取っていますよね。
富塚:
ええ、それが私のジレンマにもなっていました。一生懸命「利他」を叫んでいても、業界自体がそうじゃないですから。
不動産の投資や売買等で関わっていると、自分のこれまでの経験や身に着けたものが、本当の意味で世界の役にたたないのではないか、と思いました。
だから、自分の強みを発揮できる形で、世界の方々皆様のお役に立てるためには?と考えたことが「日本の不動産制度を海外に広める」ということだったんです。
酒井:
具体的には、どういうところを広めたいんですか?
富塚:
日本の不動産に関する素晴らしいところ。それは都市インフラ、道路。鉄道等ですね。こうした都市インフラがきれいに計画通りにできるのは、私人の方の土地を理にかなって買収する、という制度(土地収用)があるからです。こうした買収制度(土地収用制度)をサポートする一つの指標が地価公示という制度あり、これは我々不動産鑑定士が中心になって作業をしています。
ロンドンやNYは、都市インフラは整備されていますが、東京ほど鉄道網は発達していません。東京は私鉄、地下鉄、それらがスムーズに繋がってしかも安い。これってとても素晴らしいことなんですよ。
フィリピンのマニラやインドネシアのジャカルタだと、都市のインフラ自体も作るのが大変なので、日本の企業が携わっています。逆に中国みたいな土地の所有権の自由がないようなところは「はい、鉄道を敷くから家出てってね」で済むんです。

酒井:
不動産がお国柄にも出る。
富塚:
日本みたいに土地の所有権が守られている国だと、買収していく形になりますが、その仕組みも、大前提として「都市インフラを整える」というのがあり、加えて「災害対策の面も考えよう」「観光資源にもなるように整えよう」と形にしていく。これが都市計画で、このような計画が多方面から、細部にわたってしっかりできるのは日本人くらいだと思います。
酒井:
私たちが当たり前と思っていることも、外から見るとレベルが高い。
富塚:
はい。日本は加えて地震大国ということもあり、再発防止のための取り組みが素晴らしいんです。
昨年、能登の震災復興のお手伝いをしたのですが、その際、壊れた被害の程度の判定をするんです。この住家被害認定制度は東北の震災の後に設けられたんですが、役所の方は倒壊した家屋を見慣れていないので判断ができず、私たち不動産の専門家が判定をするわけです。
柱を1本1本チェックしていくのですが、それにより、一時金が出る家・仮設住宅に移れる家・立て替え工事が安く行える家…などが分類できるんです。これが新しいインフラの土台になるので、日本が生みだした素晴らしい不動産のシステムだといえます。
酒井:
確かに、「このまま住み続けたいけれど大丈夫なのか」「直すより壊した方が金銭的負担が少ないのか」などは、素人判断は厳しいですね。
富塚:
一番大事なのは人命です。
一見住めそうでも、今度大きい揺れが来たらすぐ崩れるというのは、プロにしかわかりません。
基礎の割れ方、柱の具合も国交省や内閣府のマニュアルにあって、点数の付け方も絶妙なので、その通り計算していけば耐久性の程度がわかり、記録にも残ります。
もちろん被災者さんにとっては、判定に納得できなかったり「まだ住めるじゃないか」とお叱りを受けたりすることもあります。が、とにかく丁寧に説明し、納得していただき、被災者の方が、次のステップに進むことができるお手伝いを、繰り返し行っていきます。
酒井:
富塚さんたちの判定が、被災した人の気持ちを前進させるのですね。
確かに熊本を見てみると、ちゃんとインフラが復活しています。この復興力は日本のすごいところだと思います。
富塚:
11月に台湾に行ったんですが、台北の災害対策の担当者さんと復興についての座談会をしたんです。それがとても喜ばれて。こうした意見交換を継続していけば被災地の人たちの役に立つかなと、それを最近のライフワークにしています。
酒井:
そうすると、途上国というか、地震を含め天災にあまり慣れておらず、復興のマニュアルがない国への訪問が増えそうですね。
富塚:
呼んでくださるならどこへでも伺います。インフラが整うとスラムもなくなるし、土地そのものや街の資産が上がりますよね。
インキュベーション施設のような存在というか…前述のような被害の程度を測る指針があることの便利さを伝えたいです。
不動産投資はリスクを熟考し
保有している不動産は有効活用を
酒井:
昨今の日本の不動産についてですが、実際シンプルに「買った方がいいのか、買わない方がいいのか」を伺いたいのですが。
富塚:
そうですね、私の考え方は2つあります。
1つは、この先、投資目的として買うというのはオススメしません。今サラリーマンに向けて不動産をはじめ、いろいろな投資がありますが、今持っておらず、これから買いたいというのはやめた方がいいかなと。
その理由は、今、不動産を新規に購入して儲かる仕組みにするのはすごく大変だからです。「テナントが入れば不労所得になります」と言われると思いますが、本当に入るのかと。巷でも立地がよくても空いているテナントは山ほどあります。落とし穴に注意して欲しいですね。
酒井:
リスクを考えてこその投資ですからね。

富塚:
買う時って「下がったらどうしよう」という考えがなぜか消滅する(苦笑)。入居されなかったら? そして建物自体の経年劣化は?と。身体でもメンテナンスするのに、家もメンテナンスが必要で、そこにはお金も居るという発想も知識もない。
だから欲に駆られて買わないで欲しいです。
特に海外を見て思うのは、2桁成長なんてありませんから。持っているだけでは上がらないんです。
酒井:
かつての「土地さえ持っていればいい」という神話は出ないということですね。
富塚:
ええ、私はそのように思います。そして2つ目はそれとは逆に、もし継承したり相続、譲渡されて、すでに不動産を所有している場合は、その不動産を、ぜひ有効活用をしてくださいということです。
酒井:
ない人は買わない、持っている人は頑張る。
富塚:
長く生きていると、あっという間にいい時って過ぎたり、周りから人がいなくなる事実を見聞きします。ですからもし活用するのであれば、人任せではなく自分で勉強することが大事ですね。
ファミリービジネスの観点から見ると、いろいろな考え方があり、イタリアでは「メインの事業が成功したら投資家になる」ということが王道なんです。王道を続けることがサスティナビリティの一つの考え方ですね。メインである本業はしっかりしつつ、サブの事業も「もしもの時」にしっかり備える必要があります。一族の中で一人は不動産に特化して、周りの力を借りながらキャッシュが一族に安定的に入ってくる仕組みを整えていくこと。本業が潜在的に持っているリスクを考えつつ、不動産収入という道を作っておくこと。
そして「不動産があるから大丈夫」と考えるだけでなく、マネジメントしながら、手放す時やキープしておく時を見極める。「まさかの坂」は誰にでもありますから。
酒井:
コロナの時、ある飲食店経営者が大打撃を受けました。そのような時でも、サブで不動産収入を得ていたからこそ、乗り越えられたという話を聴いたことがあります。
この社長は2台目で、継いだときはこの不動産を処分しようとしました。が、先代である父親に「その不動産は絶対に売ってはならない」ときつく言われたそうです。
結局コロナ禍でその不動産に救われたわけで、その社長は先代にとても感謝していました。
不動産も適材適所、時勢を見極めるための学びが必要と言えそうですね。
富塚:
私は、これまで遺産分割にかかわるお仕事をさせてもらうこともありました。
遺産分割の関係者、各人の心の奥底にあるものを伺い、両者をフラットに聴く経験は、ビジネスにも役立ちました。
専門的な話で遺産分割についてコメントをするなら、現金がないと大変です。税理士さんは「現金は置いておくな」という方が多いですが、不動産は分配も共有も難しい。不動産を持ちつつ、それを担保に銀行からお金を借りるのがベターかなと思いますね。
酒井:
やはり自身で学ぶことが大事なんでしょうね。
では巷でよく聞く「35年ローン」についてはどう思いますか?
富塚:
私はありだと思います。というのも自宅を買うのは投資ではないですし「学区がいい」とか「両親の実家に近い」とか、買う目的が違いますから。「そこに住みたい」という理由でローンを組んで粛々と払っていくのはいいんじゃないでしょうか。
とはいえ、払い終わった時には買った時の値段では売れませんから、それは覚悟の上で。
不動産ってお見合いと同じで、いろいろな人が「こういう条件だけど」と話を持ってきても、結局は自身の価値観で決めるもの。「そんな条件でいいの?」というのが本人にとっては「その方が楽しく生活できるから」になることもありますし。
酒井:
かくいう先生は、ご自身の持ち物として家はお持ちではないんですよね?
富塚:
私はボヘミアンなんですよ(笑)。とにかく、いつでも身軽でいたいから賃貸。それに不動産は売れない時があるし、現金化に時間がかかり、メンテナンスも必要ですから。
持ち家に関してはプロの間でも考えは分かれますね。
逆に夫は「ブラジルでは家を持てるのが豊かになった証」ということで買いたいと思うそうです。お国柄もあるかもしれません。
酒井:
時代もありますよね。私が30歳の頃、バブルが崩壊しました。その時周囲に「無理して家を買わなければよかった」とつぶやいている先輩が何人もいました。そんな経験から土地を買おうという気持ちが今でもおきないんです。
富塚:
私は身軽さ、維持管理が必要ないこと、固定資産税を払わなくてもいいこと、など考えて賃貸一択です。あとは住居と事務所を分けたいとか、最近はリモートでも仕事ができるなとか…まあ市町村によって税金の区分けが違うので、そのあたりも考えてのことです。
今後リモートがメインになると、都心に住む人が増えて地方には空き家が増えていくかもしれませんが、逆に人があまりいない駅の近くでも「交通網はあるけれど静かでいい」とか「子育てにいい」と住む人が出てくるかもしれません。
これは時代の流れも関係してくるでしょうね。その人なりの価値観がありますから。例えば酒井さんのような方には釣りも大事な要素ですし(笑)。
酒井:
確かにそうですね。誰かにとっては避ける場所でも、誰かにとっては極上に住みやすい場所かもしれませんから。
コンサルティングに算命学を用い
経営者の選択肢を広げる
酒井:
不動産業と平行して、ファミリービジネス向けのコンサルのお仕事もされていますが、そちらでは具体的にどんなことを行っているのですか?
富塚:
ファミリービジネスの資産管理としての不動産の有効活用や、ファミリービジネスのオーナーや時期後継者の方のお悩みを直接お伺いして、いろいろな角度からアドバイスを行っています。大半はお話をされる中でご自身の問題点に気づかれることが多いので、サポート的な感じでしょうか。これは日本の企業でも海外の企業でも同じです。

酒井:
アドバイスのベースにも、やはり稲盛さんの考え方が?
富塚:
「稲盛さんはこう言っていますよ」とお伝えすることもありますが、やはり「稲盛さんは、そうかもしれないが、自分は稲盛さんほどの経営者の能力があるわけではないので…」とおっしゃる方もあります(笑)。
とはいえ原理原則は同じですね。その方が潜在的に気になっているだろうことを引き出したり、本当に伝えたいことに思いを巡らせたり、心理学やメンタルブロック解消のアプローチも使っています。
酒井:
富塚さんは最近算命学を学んでいらっしゃるそうですが、それも使いますか?
富塚:
私が学んでいるのは「算命学」というのですが、やはりその方の宿命ってあるんですよ。
例えば継承ひとつとっても、「創業者運」や「二代目運」があります。仮にカリスマ的な父親が「息子に跡を継いで欲しい」といった際には息子さんを鑑定してみて、もし創業者運を持っているなら「お父さんの築いたものを継ぐより、それをベースとして活かして独自の新規事業を立ち上げるといいですよ」と伝えることもあります。カリスマ的な親は創業者運をお持ちの方が多いので、多分ご自身でやりきったら満足されことが多いですね。
酒井:
トップになると新しい事業の導入など、悩みや迷いが増えますから、コンサルタントもある程度鑑定などが使えるといいかもしれませんね。
富塚:
著名になればなるほどすがるものがない…というパターンもありますね。スピリチュアルに傾倒する、あるいは極端に合理的なるのではなく「自分とは違う視点」「柔軟な考えを加える」という面で、新たな気付きを伝えられたらと思います。算命学による鑑定はあくまでも手段のひとつとしてとらえています。
酒井:
スピリチュアルを学ぶトップの方は多いですが、富塚さんのようにガチガチのビジネス畑で活躍され、経営者でもある方はあまりいないので「富塚さんが言うのなら…」と落とし込めたり、行動が変わったりする方は多いかもしれませんね。
富塚:
できる解釈はしますが、現象は一長一短、多角的な面を持つので、鑑定で「要注意」と出ていても視点により解釈は異なります。ですから最終的にはその方の判断に委ねますが、悪い結果が出た時は一緒に反省します。そうした事実を淡々と受け止める姿勢は、合気道で学びましたね。
酒井:
ところで、富塚さんはファミリービジネスの経営者向けのメルマガも出されていますね。
富塚:
ファミリービジネスでのメルマガは月1回、算命学に基づいたことも書いていますよ。稲盛メソッド同様、アウトプットの場にもなっていますが、話題になっている企業さんについて算命学を使って分析したことなども書いていますね。「こういう鑑定が出ているからこういう性質ではないか」というような。
酒井:
そちらのメルマガはファミリービジネスの人しか読めないものですね。私は読む資格はあるのかな…?是非読んでみたいです。
富塚:
ありがとうございます。次回からお送りしますね!
酒井:
富塚先生の脳の中には、膨大なものが入っていそうですね!
経営者としてでも英語の講師としてでもメルマガを発行されていますし、本当に頭が下がります。
富塚:
英語の指導者として配信しているユキーナ・サントスメルマガでは、国際時事ネタを織り込んでいます。やはり英語の需要というか「ビジネスではどう言う」とか「こういうことを伝えるための語彙は」というご相談をよくいただくんですよ。弊社の「アブリールス・メルマガ」は自己啓発や国際ビジネス、時事ネタ、算命学等もタイムリーなネタを入れています。
あとはオープンでは書きにくいことを、メルマガで書いています。
合気道・着物道・華道
稲盛哲学に通じる「日本の文化」
酒井:
先程出た合気道の話は時折伺っていましたね。当初は仕事のために那覇にいらしたけれど、今は合気道のお師匠さんがいらっしゃるから引っ越さないとか。
富塚:
はい、そうなんです。私は黒帯三段で、合氣道の師範の山口巌先生は80歳を超えたのですが、世界一の合気道の師と思います。教えの隅々に稲盛さんとも通じるところがあるので、この先生の合氣道を学ぶために、私は沖縄にいます。釣りをするために岐阜に住まわれている酒井さんと一緒ですよ(笑)。
酒井:
そう言われると納得です(笑)。合気道って試合を一切しないとか?
富塚:
はい。試合も「はい。「演武」しかないですね。
合気道は「動く禅」と言われています。座禅と同じで体験を通して表現として身につける。究極的には「空」と「虚」と「無」を体験し、自分の体で表現します。
こだわりがあったり答えを求める人は、合気道はうまくできない。一般の方は、山口先生から、指一本で倒されてしまいます。
もちろん力学的な視点からの解明できますが、究極はメンタルの問題です。学び甲斐のある分野だと思っています。
酒井:
老若男女問わず、誰でもできるんですか?
富塚:
合気道の開祖が植芝盛平さんという方ですが、開祖はそのようにおっしゃっていたそうです。老若男女、どんな人でもできますが、実は大人よりも子どもの方が形や答えを持っていない分、うまくできます。
答えを求めず、執着せず、心を柔らかくすることを学ぶために私は合気道をやっています。
また、力に対して力で対抗することは戦いと争いであり、どちらかが壊れるまで続きます。つまり「和」には繋がらないのです。


酒井:
聴けば聴くほど奥深いですね。
富塚:
お稽古は90分ですが、お稽古の半分は山口先生のお話です。残りの半分はストレッチやヨガ、重心を落とす練習と実際に合氣道の技などをお稽古します。
合気道では、「受け身」と言って、転ぶ練習、負ける練習から入ります。それが「武道」だと思います。また、武道の究極は「受け身」だと思います。ですので前述のように身体や、その体を司る「考え」が固いと上手な受け身もできません。さらに言うなら「美しい円を描くような、丸く、柔らかで弾力のある受け身」が理想です。
酒井:
なんだか、ビジネスと通じるものがある気がします。
富塚:
そうかもしれませんね。相手の動きに沿っていくと、その流れの中でスムーズに融和する感じが似ているかもしれません。
ただこれは欠点でもあるのですが、大衆に受け入れられるためには、ある程度「形」を伝える必要があります。そうすると一番大切なものが抜け落ちてしまう。稲盛さんのフィロソフィもそうですが、「○○道」と呼ばれるものには共通していると思います。
酒井:
悩ましいところですよね。
富塚:
沖縄で改めて師匠に学び「今まで学んできた合気道とは違っていた」と反省したのですが、それは稲盛さんの本を読んで文章化し、反省する時の気持ちと似ていますね。
ビジネスも同じですが、相手の力を受け入れることで、無限の可能性を見出すことがあります。。相手がどうこうではなく、結局は自分にこだわりがあるため、なめらかに動けない、これを理解するのが合氣道なのかもしれません。このような体験をして欲しいですね。ぜひ沖縄へ!

酒井:
大変魅力的なお誘いですね。
「○○道」といえば富塚さんは着物道にも通じているとか。
富塚:
いえいえ、お恥ずかしい。通じている、というほどではありません。着物は日本の伝統であり心だと思いますね。私も過去には海外にかぶれていた時期がありましたが(苦笑)、海外で学んでから日本を見ると、日本の歴史や伝統の中に、本当に素晴らしいなと思うことがたくさんあります。
海外では、決していい着物でなくても、小紋等のカジュアルな着物でも、着物を着ているだけで、「一緒に写真を撮りましょう!」って言っていただける。雰囲気も明るくなり会話のきっかけになるのでいいですね。
台湾に行った時は、着物でテレサテンを歌うことになったり。海外で巡業している演歌歌手のような気持ちになりました。私は華道を相阿彌流という流派で約15年くらい学んでいます。日本の道事(みちごと)は世界にほかに類を見ないほど素晴らしいものだと思います。

酒井:
不動産にしても文化にしても、日本が築いてきたことを海外に発信することに邁進していらっしゃり、とても羨ましく感じます。
僕も大学で柔道同好会に所属していたので、ホームステイ先で型を披露したり、商社での勤務時大には茶道を覚える先輩もいました。こうした日本人らしさをひとつでも表現できるといいなと思いながら、40年経ってしまいましたが…。
富塚:
うちの夫はブラジル人なんですけど、友達に「俺の妻は黒帯なんだ」って言っています。「妻の自慢はそこなのか??」っていつも思うんですが(笑)、ブラジルの方に合気道を披露すると、みんな驚きますよ。日本の文化はまだまだ知られていないものも多いので、考え方や文化も含め、海外に発信していきたいです。
酒井:
改めて思えば、稲盛さんご自身が日本の文化であり、日本の精神性の凝縮ですよね。
富塚:
確かにそうですね。外国の方にスムーズに入っていきづらいのも、日本の精神性があるからでしょうね。
稲盛さんの哲学は学べば学ぶほどシンプルだけれど奥が深く、ある著書では「宇宙」というテーマから入るようなものもあります。
でも何年か学んでから改めて宇宙の章を読むと「稲盛さんは、万物の成り立ちと人間の心の根本を描きたかったんだな」と、腑に落ちたというか、しっくりきました。
酒井:
同じく経営者として松下幸之助の哲学もありますが、残念ながら稲盛さんほど体系化されていないので、富塚さんのメルマガは本当にありがたいです。しかも説教っぽくなくて。なんか、とても素直にスッと入ってくるのです。
富塚:
ありがとうございます。沖縄に住んでいますが、国内・海外、出張に行った先からも書いています。あらゆるところでメルマガを書いていますが、都度都度学びつつ、顧みつつ、日々新たな一歩を踏み出して目的に近づけるように、これからも発信し続けます。
酒井:
「エバンジェリスト」としての使命を果たしながら邁進される富塚さんのご活躍を、これからも楽しみにしています。もちろんメルマガも!
今日はありがとうございました。


プロフィール
富塚 祐子(とみづか ゆうこ)
アブリールス株式会社 代表取締役 社長
不動産鑑定士(日本)
MAI米国不動産鑑定士
MRICS英国王立不動産鑑定士
MBA(経営学修士)
再開発プランナー(全国の市街地再開発事業について計画・助言・実施) 英国王立サーベイヤー協会 アジア商業不動産理事 災害リスク管理(BCP)委員
1992年、財団法人日本不動産研究所にて表参道地区、新宿駅南口直結大型商業施設開発等を担当。
2004年よりボッコーニ大学ビジネススクール(イタリア)留学、コーネル大学ビジネススクール(アメリカ)へ交換留学。2006年、アメリカの証券会社ベアースターンズにて、商業不動産証券組成。
2007年、ドイツの不動産銀行ユーロハイポ、ドイツ系金融機関ウエストLBグループにてアジア投資案件の審査、コンサルティング、リサーチを行う。
2013年、アブリールス設立。同年より2017年までブラジル国営石油会社ペトロブラスにて経営企画・コンプライアンス補助。
2015年、ホテルコンサルティンググループ アセットリアル日本代表に就任、同年、UET ヨーロッパ観光大学(イタリアミラノ本部) 日本統括責任者 現在は、沖縄を中心に不動産鑑定、不動産投資アドバイザリー、ファミリービジネスアドバイザーとして国内外の投資家をサポート