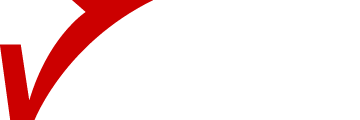戸髙一成氏

戸髙一成氏×酒井英之
まさにこれが「温故知新」
日本海軍の成功と失敗を経営に活かす
広島県・呉市の「大和ミュージアム」の館長を務め20年を迎えた、戸髙一成先生。美大卒業後に海軍について研究を重ね、財団法人史料調査会および、昭和館(戦没者追悼平和記念館)などでも活躍されてきました。
海軍の歴史と一口に言っても、日露戦争・日清戦争、そして太平洋戦争では、その位置づけや世間的価値も違いますが、その中で「失敗から学び、経営に役立てるものがある」とお話しされています。そこで今回は、海軍の成長や衰退を通して、現在の日本における人材採用や育成、経営に活かせるようなヒントを伺ってみました。
彫刻の世界からデザイン会社を経て、研究職に
酒井:
お久しぶりです。春に中小企業大学校でお話を伺って以来ですね。お忙しいところありがとうございます。

戸髙:
こちらこそありがとうございます。今日は千葉の自宅からここに来るまでに、古本屋に寄ってきたのでちょうどよかったです。
本は読まなくても「そこにある」ことが大事だと思っているので、ついつい買ってしまいますね。
酒井:
確かに、「そこにある」だけで意識が変わりますよね。
そういえば先生は図書館司書もされていましたが、大学は美大だったんですよね?
戸髙:
はい。多摩美術大学で彫刻を学んでいました。彫刻科は就職先など無いので、友人とデザイン会社を作り、5年間デザイナーをしました。その後鶴見大学の図書館講座で司書の資格を取ったんです。
小学生のころから海軍に興味が有り、大学を出た頃から海軍の研究団体である史料館(財団法人史料調査会)に足繁く通っていた際、調査会の会長から「手伝ってくれないか」と声をかけられて「いいですよ」と即答しました。当時の史料調査会では、会長も上司も元連合艦隊参謀で、上司は山本五十六長官の参謀でした、顧問的な方には戦艦「陸奥(むつ)」艦長から軍務局長になられた保科善四郎さんなどもいらっしゃったので、薄給ではありましたがお手伝いさせて頂きました。実は、月謝をお支払いしても通いたかったほどです。
酒井:
それが海軍との出会いなのですね。それから、大和ミュージアムの館長になられるまでは?
戸髙:
史料調査会では15年勤め、初の戦後生まれの財団理事に就任していましたが、平成5年に当時の厚生省から「戦争で苦労された遺族維遺児の歴史を残すために、戦没者追悼平和記念館(現在の昭和館)を設立するので、立ち上げに携わってもらえないか」と相談されました。
それで、史料調査会では唯一の戦後生まれの理事を取られるのは困ると言われましたが、理事会で承認されて移籍して設立事業を行い、平成11年に「昭和館」がオープン、同時に図書情報部長となりましたが、数年後に、今度は呉市から、呉市と海軍造船技術の歴史博物館を作りたいので、手伝って欲しい、とお声がかかりました。

酒井:
大和ミュージアムも、ゼロからの立ち上げるのはかなり大変だったのでは?
戸髙:
ええ、それまで呉市では10年以上調査と準備をしていましたが、私の着任から立ち上げまでが1年、かなり厳しいかったですね。オープンと同時に館長になりましたが、ミュージアムは呉市の施設なので、役所の担当者も次々変わり。とうとう私が最長老になりました。現在76歳になりますが「死ぬまでやってください」なんて言われたこともあります(笑)。
酒井:
いやあ、とてもお若くて76歳には見えません。でも後継者には悩むところですよね。
戸髙:
よく「最後の仕事は次の人間を決めること」と言いますが、まさにそれです。
酒井:
企業の場合は、息子や一族が継承する場合が多いですが、博物館はどうなんでしょう。
戸髙:
貴重なものを扱う性質上、安心できる方にお任せするのが最優先です。
加えて、基本的なミュージアムのコンセプトや知識を理解した上で、十分な近現代史、政治史、軍事史の知識については、少なくも博士課程程度の研究歴も欲しい。さらには学芸員としての知識と、県立・国立クラスの博物館で10年以上の実務経験を積んでいる方がいいので、かなり難しいんです。
酒井:
ハードルが高すぎますね。どこにもいないのでは(苦笑)?
戸髙:
妥協してハードルを下げて、後で後悔しても困るので、ハードルは下げずに見つけなくてはと思っています。
司馬遼太郎が「坂の上の雲」の先に見ていた景色
酒井:
さて、ご専門である海軍について「組織」という面から深掘りしたいと思います。
海軍は明治になってから作られ、大国ロシアに勝つほどの強い組織になりましたが、その後方向性がおかしくなり、敗北という結果に陥りました。
つまり、明治から昭和にかけて「強い組織と弱い組織の両方」を見てきたのが海軍だと思うのですが、詳しく教えていただけますか?

戸髙:
やはり海軍の歴史でシンボリックなのは、明治維新から日露戦争までの進歩です。
技術は戦艦大和まで高度化するものの、日露戦争以降からは制度のレベルも運用のレベルも下がってしまう。これらの経緯を紐解くのは学ぶ価値があります。
司馬遼太郎さんの有名な「坂の上の雲」も大変な傑作ですが、実は坂を上りきった先は断崖絶壁だったのですよ。そして「坂を上った先」にあるノモンハン事件を書こうとしていた矢先に、先生は旅立たれましたが…。
酒井:
日露戦争の時にはすでにレベルが下がりはじめていたんですね。
戸髙:
そうなんです。
あまり知られていませんが、海軍以前、つまり江戸時代の日本人はよく考え、世界をよく知っていたんです。
開国という大きな出来事もありましたが、それに順応して生きてきた江戸の人たちが優秀で、その江戸の人が作ったから明治は素晴らしい時代なんです。
逆に明治を生きた人は昭和になってから日本をつぶしました(苦笑)。明治維新がすごいのではなく、その礎を作った江戸の人たちがすごいという、時間軸のギャップの面白さがあります。
酒井:
江戸時代の日本人の方が柔軟な考えを持ち、外国を知っていた。
戸髙:
心を落ち着けて、何が大事で、そのために何が必要か熟考したのでしょうね。
明治維新も実質2年かかり、当初海軍も「作らなきゃ」と半ば脅される形で作りましたが、まず理想型を考えに考え「海軍を作るためにまず学校を作り、軍人を養成することが第一である」という結論に達しました。つまり教育がまず第一歩だと。そして政府の投資がスタートしたんです。
酒井:
箱ではなく、何よりも人を養成する。
戸髙:
軍艦を買うとか軍備のための調達や技術よりも「教育」最優先。それが海軍の成功に結びつきました。
軍艦を買ったら教師も雇って教育する。それまでは咸臨丸の時もそうですが、出来上がった軍艦が来るのを日本で待っていました。
が、明治の途中から買った軍艦を欧州の現地で引き渡してもらいます。そこで操縦法を教わり、その軍艦に乗って帰国するスタイルにしたんです。
その際、幹部士官はもちろん10代の見習い、いわゆる水兵など何百人が現地に行き、かなり充実した教育を受けました。軍艦『三笠』などでは500人以上が行ったでしょうか。これが何隻もあるのですから、当時の海軍には数千人のヨーロッパ経験者が居たと言うことになります。
酒井:
ごく限られたエリートしか外国に行けなかった明治時代に、数千人?
戸髙:
技術を持って帰るために、海軍だけは10代の少年でもフランスやドイツに行けたんですよ。幹部だと1年くらい実際に住んで、文化や環境、考え方などを実体験として学べたので、当時のヨーロッパのリアルを知っているんです。
技術を覚えたら軍艦に乗って帰国しますが、19世紀にはスエズ運河がないので、アフリカ経由で植民地にされた国をたどってくるわけです。そこで「こんな目に遭っているのか…」という現実を見せられる。当時の海軍は幹部から水平に至るまで、リアルタイムで恵まれている国と植民地にされた国を見てきたんです。
酒井:
辛い帰り道ですね…。
戸髙:
こういう経験を経て、日露戦争の頃は、該当する人間が外国と戦うための勉強や訓練に励めました。こうして積み上げたものが日清・日露戦争での海軍の進歩のバックグラウンドになったと思います。
酒井:
そう考えると、やはり勉強って大事だと改めて感じます。何も知らなければ、良い悪いの判断ができません。
戸髙:
その能力を与えられたのが当時の海軍で、初期のエンジニアや幹部はイギリスで学べる経験もできた。極秘のものを日本には公開してくれたので、帰国してそのスキルを造船所で伝えられました。ここまでは「坂の上」の坂道を上がってきたといえますね。
酒井:
なるほど。留学も含めて教育制度が優れていたのですね。では細かな仕組み作りや体制はどのように整えたのでしょうか?
古今東西、若者のやる気を出すには、何が必要か?
戸髙:
船乗りは職人集団ですが、知識だけでできる仕事ではなく、操作して作戦を立てて戦って、初めて価値を発揮できるんです。
こうした優秀な工員を育てるには、頭が良くて健康で、やる気がある子どもが欲しい。
しかし、明治維新後の日本で、向上心のある若者は東京に出て政治家や実業家を目指す若者が多いので、優秀で健康な子を集めるために、まず身分制度を整えたんです。
酒井:
身分制度?
戸髙:
はい。工員でも経済的に恵まれなくても、海軍の技術者になれば、経済的に恵まれて、かつ十分な教育を受けた帝大卒の若者と同じように、ステップアップできる仕組みを整えたんですよ。
地方在住で経済的に恵まれていなくても、能力さえあれば、地元で勤務しながら経験を積めば、東京の大学に進学した若者と同じエリートになれると。
海軍は、海軍工廠などで軍艦建造の中心になる中堅工員を技手(ぎて)と呼んで重視し、「技手養成所」を作り若者を集めた。技手はステップアップして、当時の役人の身分で奏任官まで行ける制度にしたのです。奏任官は海軍士官ならば大佐クラス、エリートです。これを見た若者は、それこそ「大学に行くか技手養成所に行くか」くらいの魅力を感じて、大変な倍率になったんです。要するに、プライドを持てる身分を作った。

酒井:
若者のやる気に火を点ける、なかなかいい制度ですね。
戸髙:
海軍工廠では基礎学問は教室で行い、一定のところまで行ったら現場に移ってモノ作りを教わり、それが一定のレベルになったら教室に戻り…と繰り返しながら学びました。
これは兵学校でも同じで、卒業後に艦隊に行き、その後希望によって大砲や通信技術や航海術などの専門分野の学校で学び、再度艦隊で実務を行い、次は同じ学校の高等科で更に高度な知識を学び…と繰り返した。知識と現場の両方から養成したんですね。
酒井:
学んで実践、さらに専門的なことも学んだら、また実践。
戸髙:
私も美大時代、石彫などではまずノミを作るのですが、見た目は教科書通りなのに、実際使うとすぐにダメになる。ふと見ると先生のノミはずっと尖ったまま。それで山ほどヤケドしながら「知識と作る力は違う」とやっと理解する。知識と実地を重ね、精度を上げるために努力するところは、規模は違いますが海軍と同じだと思いますね。
知識だけでは作れないし、現場経験だけでは限界があります。
酒井:
よくわかります。が、これを企業経営に置き換えてみると、現場の人はギリギリの人数でやっているから、知識を得る機会もなくそのまま年を重ねてしまうケースが実に多い。
戸髙:
それはもったいないですよね。知識と現場経験、その両方があってはじめて次の育成を育成できます。これらを仕組化して実践したのが海軍ではないでしょうか。
酒井:
最近は、若い人が働きやすい職場として「心理的な安全」を求めている傾向にあります。
まずは「ここで自分は必要とされているか」「周囲とうまくやれるか」という精神的なものがあり、次に「頑張ればここまで行けるから大丈夫」という、キャリアに対する安心感を求めています。
戸髙:
会社は本来、社員にこの組織にいる安心感を与える存在でないといけません。管理運営も重要で、海軍のように「頑張ればキャリアアップできる。将来はもっと良くなる」という安心感は健全で、当時の若者が安心して働ける仕組みだったと思います。
隠してきた戦争の真実が、後の失敗を引き起こす
戸髙:
ただ、のちに海軍は失敗します。それを引き起こしたのが、トップの意識の後退と欠落。
確かに日本は日露戦争で恩恵を受けましたが、褒美として爵位をばらまいたんですよ。当時の社会の中で華族になるのは難しいので、お金よりも価値がありました。
酒井:
爵位をもらえれば天皇陛下の部下ですから、末代までの名誉ですね。
戸髙:
それに、政府にとって、名誉を与える方が財政負担もない(笑)。
まあそんな感じで恩恵を受けたのち、日露戦争に参加できなかった次世代、例えば山本五十六などの世代は学校を卒業した瞬間、意気揚々として戦争に臨むわけですよ。でも戦争は終わってしまって。
「あ~あ、もう一度戦争が起きれば」「戦争さえあれば出世できるのに」という刷り込みが成されたんでしょうね。
酒井:
戦争さえあれば大恩恵を受けられるという「戦争を待ち望む」潜在的な気持ちが、まん延していったのですね。
戸髙:
それが一番悪かったと思います。
加えて、本当は「なんとか勝った」だけなのに、軍人は見栄を張って成功体験しか話さない。今振り返るとそれは明らかで、もう一戦していたら負けていた。実際、賠償金も十分には無いままに講和条約を結び、国民も「賠償金がないじゃいか」と憤り、日比谷焼き討ち事件があったわけですから。
政府も軍も「圧勝だった」と言う。いつの時代も外野にいるのが、国民なのかもしれませんが…。
酒井:
こうしたことは、軍も正確に捉えていたのでしょうか。
戸髙:
海軍が戦史をまとめた4冊の公刊戦史には、勝った話しか書いてないのですが、数組の極秘戦史が作られて、1組だけ、皇室に献上したものが防衛研究所に保管してあるんです。その数、なんと150冊。そこにはリアルな歴史が綴られています。毎日ドタバタしていて、ああでもないこうでもないと大騒ぎ。苦労したのが伝わってきますね。
これは軍人にも読む機会はなく、一般に出回っている本には「日本は強い」と書いてあった。
「われわれは強い。勝てる」という悪い思い込みの温床が、その後のつまずきの第一歩だったんですね。
酒井:
失敗を隠して学ばないから、『坂の上の雲』の先の断崖絶壁から、日本は転げ落ちてしまった…

戸髙:
のちの第一次世界大戦でも、同じミスをします。このとき日本海軍は、日英同盟の義理で少し手伝っただけで、凄まじい戦いを経験しませんでした。
この大戦で、一部の人だけが「これは大変だ、国家総力戦だ」と慌てて「戦闘の大きさも段違いで、陸上戦で1日に何万の人が死ぬ」という実態を知りましたが、表面上は戦勝国ですからね。「われわれは強い。勝てる」の想いが強くなりました。
酒井:
「また戦争があれば、いいことが起きる」くらいの気持ちだったかもしれませんね。
戸髙:
兵学校の校長をされていた新見政一さんという方がヨーロッパの史料で第一次世界大戦の研究をし、書いたものがあります。私も仲良くさせてもらっているのですが、戦争の規模や悲惨さを書いているのに、太平洋戦争の際に指揮官やトップは誰も読まなかったのです。
新見さんの研究は大変立派であり、そういう方が指揮官になるべきだったんですが…。
酒井:
「失敗を次に活かしましょう」という講義はされなかったのでしょうか?
戸髙:
一部のトップやエリートが少し学ぶだけで、片手間というか一生懸命ではない。「アメリカにどう勝つか」は勉強するけれど、防衛や輸送の話は「自分たちの専門じゃない」と。ロジスティックに関して学ばなかったことが蓄積されていったんです。
もうひとつ遡ると、日露戦争後から大正になった頃、第一次世界大戦により船を輸出する造船バブルが起こりました。しかも想像つかないレベルの。
酒井:
教科書のイラストでよく見た「成金」ですね。
高い技術を守るため、別格扱いだった軍艦
戸髙:
料亭から出る時に足元が暗くて見えないから、10円札に火をつけた風刺絵ですね。
結局戦争に対する深刻感が育たないまま時が過ぎていきます。
これとは逆に、当時のアメリカやヨーロッパは大変で、経済や人員が破綻し、勝った国も負けた国も復興に躍起になっていた。
対して日本は軍艦の作り放題で、海軍が国家予算の半分近くになりかかっていた。
酒井:
国家予算の半分を使う計画が通ってしまうとは!
戸髙:
諸外国は「海軍力を縮小しよう」とワシントン会議を開き、日本も条約を飲みましたが、条約の中に「10年間主力艦(戦艦・巡洋戦艦)を作らない」というのがあったんです。
しかし10年も作らないと現場には戦艦を作れる工員がいなくなり、次作る時には技術が途絶え、明治からやり直しになる。それを危惧して軍艦だけは作れたんです。
酒井:
せっかくの技術、知の伝承をしなければいけないですね。

戸髙:
戦艦は通常の船と違って特殊な作りで、実際の戦艦に関わって手を動かさないと勉強にならないんです。
例えば装甲鈑は40㎝もの厚みのものを使いますから。普通の船ではなく「戦艦」を触る勉強をしないと経験が積めない。
そこで、条約の範囲である10隻のうち数隻を常に改装したり、パーツを入れ替えたりバージョンアップしたりと工事をしては工員に戦艦を触らせていたのです。
酒井:
故障もしていないのに、なぜか修理期間が異様に長い(笑)。
戸髙:
戦艦金剛など、横須賀工廠から5年も出てこないので、新品が出来るのでは?というほど(笑)。戦艦大和の設計主任だった牧野さんという方に聞いたことが有りますが、
「技術の維持には本物を触らせなくてはならない、それがカリキュラムのようにやりくりしながら、技術を維持してきたのだよ」と。
国内には海軍2か所、民間2か所、計4ヶ所の戦艦建造能力のある造船所がありましたが、海軍は仕事を均等にまわし、戦艦を作る能力を維持させていたんです。
酒井:
こうした努力で、技術や行員、現場の能力が守れた。
戸髙:
むしろ、どんどん新しい技術を入れていったので、昭和の初期には技術が向上していったんです。
酒井:
そしていよいよ大和が作られるわけですね。
どんな面から見ても世界最高レベルだった「戦艦大和」
戸髙:
通常、世界最大級のものを作る場合、初めてのことばかりなのでトラブルが起こり、工期が伸びることは有るのですが、大和は2回も工期を短縮させ、半年前倒しで完成したことは大いなる功績です。世界一の船を初めて作ったとは思えません。
昭和初期に、金融恐慌で川崎重工業が潰れるというアクシデントに見舞われたのですが、海軍大臣の岡田啓介が「すぐ官営にして仕事も工員も維持しろ」と指示しました。当然もめましたが、戦艦を造れるのは4ヶ所しかないんだから、その25%が失われるのは許されないと言われたそうです。
酒井:
90年代に、政府が金融機関を再生した道筋と似ていますね…
戸髙:
そうですね。
大きい造船所が維持できたのはよかったと思います。
工業製品というのは、完成ではなく結果を出してこそ有能とされます。
最高の性能を持つ自動車を作っても「初心者がぶつけました」ではダメ。作る技術と使う技術がともに高度な上で、二者の能力を半々にして結果を出すものなんです。
その点で「凄い軍艦を作ったが、動かせるのか?」という不安がありました。
酒井:
具体的には作戦や戦略ですね。
戸髙:
はい、不安は的中し、完全に勉強が立ち後れました。主にロジスティックな面です。トップクラスの技術で作られたのに使う能力がない。とりあえず軍を作って防衛するハード面だけが整えられた。
明治時代には「戦術か造船」を学んで来ましたが、戦術を選ぶ学生は少なく、ハードは優れていたけれど能力が追いつかなかった。
もし客観的に把握できていれば、海軍や戦艦は武力衝突の抑止力として、外交で成果を上げるのためのツールになるのでしょうが、上手に使う能力を持っていなかったんです。
酒井:
外交が失敗して戦争になる。
戸髙:
はい。日露戦争で作戦を立案した秋山真之は「戦って勝つのは下手な勝ち方。戦わず勝つのがいい」と語っています。
まずは外堀を固め、外交で様子を見ながら財政や戦術戦略を整え、どうにもならなかったら実力行使が正当な流れですから。
ところが、運悪く秋山の直弟子にあたる作戦を立てられる年代の生徒が、太平洋戦争の際にはいなくなっていた。早めにリタイアしたり、まさかの事故で亡くなったり、特に大角岑生(みねお)なんて志那事変で、飛行機事故で亡くなりましたから。
酒井:
秋山真之から多くを学んだ人が、現場に誰もいなかったんですね。
戸髙:
日露戦争の時には、国債が売れましたし、アメリカでの世論誘導もあって親日派が増え、加えて、加藤友三郎・秋山真之・東郷平八郎のベストメンバーが、イギリス製の新鋭軍艦でロシアを待ち受けていました。最新技術の無線送信機なども備え、勝つべくして勝ちました。しかし、太平洋戦争の時には親日誘導も国債もあてにならず、戦艦も古いものばかり。まだ武蔵も大和もない…。
酒井:
戦略家はゼロだったのでしょうか。
戸髙:
海軍幹部は、日露戦争を経て兵学校に入ってきたから、冷静に考えたら勝てないのに、鼻息荒く「太平洋でアメリカと戦うんだ!」と刷り込まれている。そんな状態での開戦だったので、日本はご破算となりました。
ただ、日本の真面目さもあり、技術はしっかり受け継がれ、終戦の翌年には造船が復活、10年後の昭和31年には造船量世界一になりました。
酒井:
軍艦を作っていた職人にとっては、貨物船はお手のものだったでしょうね。
戸髙:
たやすかったでしょうね。何がすごいって、注文を受けた通りに造れること。しかも昨日まで戦争していた相手に。
やはり、戦争さえなければ、いいものが作れるんですよね。
技術の成果を発揮するには、平和が一番だと…それが戦争の歴史における結論のひとつだと思います。
酒井:
挫折しながらも同じ技術を持ちながら、復活している。
技術、政治、外交…、どの面から見ても明治から昭和のドラマは興味深いですね。
日露戦争とバブル時代の共通点
戸髙:
来年は終戦80年、明治維新から終戦は77年。両方の年表を重ねて比較していくと興味深いです。バブルや神武景気、コロナパニックなど、形は違っても考え方は繰り返されるので、失敗が活かされているのかなと。
酒井:
先程刷り込みの話が出ましたが、今の日本もバブルの刷り込みがある。単なる停滞期かもしれないのに、日露戦争のように「あの時の栄光を…」と期待してしまう。
戸髙:
あ、酒井先生、随分反省されていますね(笑)。
酒井:
確かにどこかで「またああいう時代が来ないかな」という妄想はあります(苦笑)。

戸髙:
上昇志向は必要ですが、単なる弾みでの上昇は意味がない。「バブルに比べると貧しい」と考えがちですが、昭和40年代に比べれば今はエネルギー問題も解消されています。
車があり、家族で海外旅行も行ける。「貧しい」の対語が「豊か」ではなく「贅沢」になっているのでギャップを感じるだけなのでは?
社会教育をすれば「日本の生活もよくなっているな」と感じられると思うんです。
酒井:
私も「バブルの時はいい思いしたんですよね~」なんてよく言われますしね。
戸髙:
バブルに基準を持たない感覚の方が、今を嘆かなくて済むと思います。
それにどんなに技術が進み、AIが発達したとしてもベースは人間。人間がプログラムしたことをやるわけですからこそ、人間は「考える」べき。
どうあるべきか、どうするべきか、しっかりと「ものを考える」。
特に人材の育成は機械ではできないですから。
トップにしかできない仕事、やらねばならない仕事
酒井:
人材育成の面では、当時は抜擢人事があったそうですね。
戸髙:
例えば西郷從道という海軍大臣がいました。西郷隆盛の弟ですが、山本権兵衛とともに、すごい数のリストラと抜擢を決行したんです。長官クラスを何人もいきなりクビにしたりしました。理由は、戊辰戦争で手柄を立てて残っている人だけど、船にも乗ってなくて勉強もしていないから。そういう人をリストラして、戦略や戦術、軍の運営に関することをしっかり学んだ人を取り立てたのです。
こういう抜擢で大事なのは、現場をよく見て、要・不要が判断できるトップであることです。
酒井:
とはいえ、意見をする人と実施する人の間にギャップがありますよね。
戸髙:
はい。通常、決定権者は既に現場を離れているので、ギャップを埋める必要があります。
この時は西郷從道が山本権兵衛に「私はわからないから、お前に任せる。全ての責任は私が取る」と。それで権兵衛が周りから圧力をかけられても「私は、西郷さんに任されています。私の言葉は西郷さんの言葉です」と乗り切ったそうです。
上が理解して、自らの全権を渡す。何かあったら上司が「あいつの言うとおりだ」と明言すればいい。
酒井:
現場にいる人を、上が自分の権限で支えるという構図ですね。
戸髙:
そもそも山本権兵衛は態度が大きくて「権兵衛大臣」なんて言われてきましたが、しっかり從道の後ろ盾があったんですよね。
こうした面で考えると、大和ミュージアムでも私は自由にさせてもらっています。
民間が呉市から受託された企業の社員だけど、人事権は呉市があるという状況です。館長への就任を依頼された時に「私、わがままですが思い通りにやらせてもらえますか」なんて言ったのですが、当時の市長さんに「思い通りにやってください」と言ってもらった。資料集めでは、ずいぶん無理なこともしました(苦笑)。
酒井:
いや、博物館こそそうでないと!
知識だけなら本があるけれど、博物館は本物があるからいいのです。
恐竜の骨と同じで全体像が見たい。
「こんな技術で戦艦大和を造っていたのか」というインパクトが重要だと思います。
戸髙:
確かに、それが博物館の魅力でありメリットですよね。
話は戻りますが、山本五十六は、三国同盟反対姿勢のためにテロに会いそうになって、米内光正海軍大臣が連合艦隊御司令長官にして、安全な海に逃がしたと言われえていますが、国防の要の人事をこんなことに使うのは間違いです。山本長官だって不本意では無かったかと思う。更に、長官としての任務に忠実になるために息の合った参謀長を欲しいのに、気に入らない参謀長を押し付けられてしまう。
酒井:
人事権は無かったのですね
戸髙:
一度は断りますが、結局は押し切られる。結果、参謀長とは仲が悪く、あまり口もきかなかったようですからね。
明治にあった細やかなソフト面が、昭和に入るとなくなってしまった。
「違うな」と思って働いていると力が出せません。全力を出して働く上で、人事的な環境を整えなくては。
酒井:
働く人の環境を整えるのが、上の人や人事の仕事ですよね。
戸髙:
はい。加えて指示系統も大事です。
開戦時、天皇と作戦を立てるのは軍令部で、実際に戦い方を指示するのは連合艦隊でした。
これでは一見、命令元が二つあるようで、現場が困る。こうした小さな困りごとが、戦争が始まった時の海軍には山ほどありました。
ハワイ作戦の時も、五十六と軍令部が論争しているので、下から見ると「もめてるなあ」という印象になる。仕事の命令は1本じゃないと現場が困るんですよね。
その後も、こういった制度上の祖語は続きます。
酒井:
こうしたことを現代の会社で例えると、中間管理職のようなものでしょうか。
課長クラスがしっかりしていないといけないし、そこを飛び越して上層部が急に現場に口出ししても迷惑ですよね。
戸髙:
指示は明確にし、「ここまではこちら、あとは自分の判断で」と線引きをする。途中で変えられると現場はいやになっちゃう。
現場の人間は、上司は知識も経験もあるプロだと理解して信頼する。現場に口を挟まずに働きやすい環境を作るのが、上の仕事だと思います。
酒井:
年長者として、つい現場の人と張り合おうとしちゃうんでしょうかね。
戸髙:
それが一番ダメです(笑)。
私は戦争を扱う仕事上、絶対的にダメなことだけは言いますが、普通はほとんど口出ししないので、たぶん「お茶飲んでお菓子食べて、居眠りしているおじいさん」って思われているでしょうね(笑)。それで20年経ちました。
何でも機械でできる現代だからこそ、人間の叡智を発揮すべき
酒井:
さて、海軍のこれまでの歴史を鑑み、分析した上で、昨今の経営者に向けてどんなことを伝えたいですか?
戸髙:
人材育成に関しては、自分がどうあるべきかを考えること。
先程もAIについて述べましたが、決して機械にはできない、変わりがきかないことが残ると思うんです。
例えば、仕事の内容を精査して思考し、目標に到達すような「先を読む力」は機械にはない。ですから今こそ人間の「考える力」をしっかり活かさないといけないと感じます。
学校の講演などでもお話ししているのですが、数々の生き物の中で、なぜ人間は生物界の頂点に立ったのかというと、人間にはモノを考える能力があったからなんです。
人間なんて水中に5分といられないし、飛べないし、走っても動物にだいたい負ける。だからこそ「ものを考える」ということに、人間は一番の要素を持っていかないといけないと思うんです。

酒井:
空想力もそうですよね。
戸髙:
「妄想」でもいいです。「こうだったらいいのにな」という気持ちや「これが欲しい」という願望がスイッチになる。
前述のように、悲惨な植民地の状態を目の当たりにしたことで「こうなりたくない!」と強く思い、その気持ちが日本の独立を守った。
その結果、100数十年以上前に、外務省などのエリートでもない学生や、船の雑用を担う人までが何千人もヨーロッパで生活したんですから。
酒井:
海外に精通した人が多かったというより、密度が濃かったのが明治の海軍ですね。
戸髙:
こういう経験があって、日清・日露戦争での対外戦争で、先進国レベルの戦いができた。
日清戦争では東郷さんもいろいろなクレームを受けましたが、国際法上は問題ないとイギリスからも認められた。そうした知識がしっかりあるような人が、海軍を支えてきたわけです。
酒井:
「国際感覚」のようなものが、諸外国と差がなかったんですね。
戸髙:
アジアでは突出していました。特に日本の留学生は真面目ですから、勉強してそれを国に還元しなくてはという気持ちが強い。逆に中国の学生は蓄積したらすぐ役人を辞めて国に返さず、自分で会社を興す人が多かったそうです。
酒井:
会社のお金でMBAを取って、取得したらすぐ会社を辞めちゃうひと頃のわが国のエリートと同じですね。
戸髙:
これらを中国はお金で解決してきた。ドイツから軍艦を買って、人員はアメリカから連れてくる。だから引き受けてくれた人が辞めたらゼロになる。やっぱり国内で人材を養成しないと続かないんです。
それと同じで、継続できない組織はないのと同じ。目先だけ良ければいいのではなく、2代目、3代目と100年続いてこそ、しっかりした組織になるんだと思います。
呉市でも、百年以上続いている企業で「何かやろう」と会を発足して「百年会」って名付けようとしたのですが、私が相談されて、いや、気持ちは大きくしよう」って「千年会」って名前を提案したんですよ。結局千年会になった。
酒井:
現状よりも上を目指すのは大原則ですよね。目線を上げて気持ちは大きく、しっかり願望を描く。
若い人にはここまで詳しく知られていないでしょうが、海軍から学ぶべきことはたくさんありますね。もっと多くの若者に、歴史を紐解くことで未来の失敗が防げることを知って欲しいです。
本日は貴重なお話をありがとうございました。


プロフィール
戸髙 一成(とだか かずしげ)
昭和23年、宮崎県出身。
昭和48年、多摩美術大学美術学部卒業後、友人とデザイン会社を設立。
平成4年、(財)史料調査会の理事就任し、平成11年には厚労省所管「昭和館」図書情報部長に就任。
平成16年、呉市企画部参事補就任、翌年、呉市海事歴史科学館 館長就任。
著書に「戦艦大和復元プロジェクト」、「戦艦大和に捧ぐ」、「聞き書き・日本海軍史」。
「『証言録』海軍反省会」では、第67回菊池寛賞受賞。
「海戦からみた太平洋戦争」、「海戦からみた日清戦争」、「海戦からみた日露戦争」他。
編・監訳に「戦艦大和・武蔵 設計と建造」、「秋山真之戦術論集」、「マハン海軍戦略」。
共著に「日本海軍史」、「日本陸海軍事典」、「日本海軍はなぜ誤ったか」。
部分執筆としてオックスフォード大学出版部から発行された「海事歴史百科辞典」全4巻(The Oxford Encyclopedia of Maritime History・2007)に東郷平八郎や呉海軍工廠などの項目を執筆。