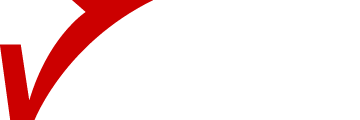竹内在氏

竹内在氏×酒井英之
100年企業を創出する
事業承継のプラットフォーマー
今回は、セレンディップ・ホールディングス株式会社代表取締役社長の竹内 在さんをお訪ねしました。わが国の企業の99%が中小企業であり、その大半が後継者に悩む昨今、「中小企業の近代化と100年企業の創出」を経営理念に、M&Aやプロ経営者の派遣、企業の体幹を強くする仕組みの構築など、事業承継のプラットホームカンパニーとして最善の継承と新体制の提案を続けていらっしゃいます。竹内さんとの出会いは、実は四半世紀ほど前。東海総合研究所の上司と部下としてのご縁がきっかけでした。そんな竹内さんに、目覚ましい成長とこれまでの道のり、さらには日本における事業継承の課題と今後の改善策などを語っていただきました。
奥ゆかしい気質を持った
東海地方の中小企業を中心に全面応援
酒井:
本当にお久しぶりですね。ゆっくりお話しするのは20年ぶり以上でしょうか?
最近の活躍に驚いています。在さんを見ていると「燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや」という中国の故事を思い出します。在さんに出会ったのは1999年。当時の私には、大きな志を持った在さんの可能性がわかりませんでした。いやはや自分の不明を恥じるばかりです。
竹内:
いえいえ、恐縮です。酒井さんには2年間、東海総研でお世話になりました。
酒井:
懐かしいですね。その頃から在さんはベンチャー企業の支援をされていました。が、上司としては「ベンチャーもいいけれど、もっと資金的に余裕があるクライアントに行ったら…」なんて思っていました(苦笑)。そっちの方が収益は大きいですから。でも志自体は、今も変わっていないのですね。
竹内:
四半世紀前から全く変わっていませんね。当時一緒に支援していた仲間と今も働いていますから、友達と仕事をしているような感じです(笑)。

酒井:
湘南出身の在さんが当時から東海エリアに中心に支援されていましたが、何かこだわりがあったんですか。
竹内:
このエリアにはすばらしい技術力を持っている製造業が多いのに、上手く情報発信できていないことに勿体なさを感じていました。
酒井:
具体的には?
竹内:
多くを語らずに地道に良いものを作り続ける。ひと言で言えば奥ゆかしさでしょうか。
世界に通じる最高品質レベルのものづくりをしているにもかかわらず、プロモーションひとつ取っても上手くいかない印象を持っています」「あの会社、本社は愛知県だったの?」という企業が実に多い(笑)。
酒井:
確かに…そのあたりは上手くないですね。特にトヨタ関連のグループ会社は知られていない名前もありますから。
竹内:
はい。
事業規模が比較的大きい、売上数百億クラスの中堅企業であっても、一般に知られていないことも多く、もったいなく感じています。会社の価値や魅力を伝えていかないと、これからの時代は採用一つとっても難しくなってしまいます。
これまではある程度採用募集をかければ人材が集まっていましたが、10年ほど前から採用環境は厳しさを増しており、募集をかけても新卒が全く集まらないという事態が続いています。
酒井:
こんなに新卒の方が不足しているのは、有史以来初めてですもんね。
竹内:
人口の減り幅が尋常じゃないですからね。知名度の高い大手企業の採用は堅調なようですが……大学だけでなく、工業高校や高専における新卒の求人倍率は毎年うなぎのぼりです。なので、なおさら中小企業を選んでくれない。来年以降ももっと大変になるでしょうから、早く手を打たないとじり貧になってしまいます。
酒井:
そういう会社で、かつ御社のグループに入っているのは後継者がいない企業さんですか?
竹内:
事業継承も多様化し、様々なパターンがあります。オーナーが高齢で経営の継続が難しかったり、ワークライフバランスを考えて50代でアーリーリタイヤを考えている方も増えています。子供がいても、本人に引き継ぐ意思のないケースも増えています。
さらには、株主としては売却したいけど、社長は続けたい…という希望もあります。それぞれの人生観や経営者としてスタンスがあるので、個々のニーズに合わせています。
酒井:
株式は売却するけれど社長は続けたいケースもあるのですか?
竹内:
はい。株式を売却し、現金化して、ワークライフバランスを保ちたいという人が増えています。70歳近くになって、会社を売却して大金を手に入れても、そのあと楽しめる残りの人生は少ないですからね。
昔は「おじいさんが作った会社だから、親族内で株式も経営も代々引き継がなきゃ」というのが一般的でした。最近は、会社は経営はするけれど、株式は第三者に売却するという形が増えています。
酒井:
経営と所有が分離しているということですね。でも普通はお金を手にしたら働かないのでは?
竹内:
不思議なもので、お金が潤沢にあっても60歳くらいの若い方なら「社会と関わっていたい」という気持ちを持つ方が多く、経営者として継続を希望される方のほうが多いです。
未来を描き、仲間として加わる
第三の継承の形を提案
酒井:
世の中にはいろいろな継承のやり方があると思うのですが、貴社のやり方を教えてください。
竹内:
一般に多いのは、同業者やファンドに売却するというやり方です。が、第三の選択肢として、「自社を成長させてくれるプラットフォーム」としてセレンディップを選んでもらっています。
オーナーの多くは、「適切な経営体制を築き、従業員・製品・技術を愛してくれる人に次世代を任せたい」という想いを持っています。したがって、私どもも「未来像を一緒に描きましょう」と、将来のあるべき姿をオーナーさんと一緒につくるようオファーします。
やはりファンドに売却すると、数年後には転売されてしまう。同業者に売却すると、会社ごと取り込まれてしまう。でもセレンディップなら、会社をいかによくして、人も技術も成長させていくかを考えるので、前者2つよりは採用されやすいと思います。
酒井:
会社を売って引退したい人もいるけれど、未来を一緒に作ろうという想いを引き継ぐんですね。

竹内:
オーナーとは共同経営というマインドを共有しています。オーナーへの買収価格の提示においても、セレンディップが一番高い金額でなかった場合でも、当社を選んでもらうことが多くあります。
そのかわり、企業価値を高める成長投資を積極的に行うことを約束しています。追加投資をしないと成長しないですからね。
当社はファンドと異なり売却前提ではなく、成長を前提に経営をする、そこが違うことに理解と共感を得てもらうようにしています。
酒井:
売り手と買い手という関係ではないということですね。
竹内:
ええ。当社を始めたばかりの頃は「苦しくなったら逃げるんでしょ」、「コンサルティングやIT畑出身の人が製造業の経営ができるの?」なんてよく言われて、なかなか信じてもらえませんでした。できることを結果で証明するしかないのですが、一緒に戦っていく従業員からも信じてもらえないのは苦しかったですね。
でも少しずつ実績ができ、2021年に上場したことで、ようやく信頼してもらえるようになってきました。
酒井:
転売するのでは? と疑われたり…。
竹内:
オーナーさんだけでなく、従業員さんや取引先さんにまで疑われました(苦笑)。ただ、こうした実績ができてきたことによって、「不安になられている方に、実際の事例を紹介できるようになりました。それでも信じてもらえない場合は、すでにグループ化した承継企業を紹介し、工場見学をしたり、経営陣や社員を紹介したりしています。社員の誰かにこっそり承継後の本音を訊いてもらってもいいですよ」とお伝えしています。
酒井:
さすがですね。
こうして成功事例は増えたわけですが、引き継ぐ節目にはどんな例があるんですか?
竹内:
先行きに不安を抱えているオーナーは多くいます。自身の健康だけでなく、自社や業界の将来に対する不安は尽きません。経営の難易度が高まる中で、特に自動車業界は電気自動車など、技術的にも大きな変革期を迎えています。向こう5年から10年の将来を考えると、このタイミングで事業承継を…と節目とするケースが一番多いです。
また、オーナーが急逝されるというケースも少なくありません。ある日突然お父様が亡くなり「長男だから引き継がざるを得なくて…」と、混迷を極めているケースもあります。その方は普通の会社員でしたから経営の知識もなく、多額の相続税を支払わざるを得なくなり、大変ご苦労されていました。
酒井:
次の社長を務める方は、在さんの会社から送り込むのですか?
竹内:
そうですね。外部からヘッドハンティングする場合と社内のプロパーから選ぶ場合があります。当社の経営スタイルは、「チーム経営」です。残念ながらスーパーマンのように何でもできる万能型の社長はいません。経営チームとして、社長だけでなく、財務や技術のトップ人材も当社が派遣するケースもあります。会社の置かれている状況や企業文化・気質を見てオーダーメイドするので、時と場合によりますね。これが当社で実施している経営者派遣です。
酒井:
プロパーの社員が社長に就くパターンもありますか?
竹内:
僕らの考えは、プロパーである・ないにかかわらず、経営チームとして力になりたいということ。ですから社長1人ではなく右腕・左腕人材とワンチームにし、プロジェクトの進捗に応じて、必要な人材を入れ替えていくスタイルにしていきます。
例えば財務の見える化であれば、きちんと役員会を開催できるよう、上場企業の管理基準を満たす人材を送り、予算から月次・四半期・年次決算業務、資金繰り、棚卸、管理規定の導入、財務分析などなど順次導入し、オペレーションを固めていく。基本的にはCEO、CFO、CTOをセットにしています。買収後数年たった会社の中には、取締役会・経営幹部メンバーがすべてプロパー社員という会社も出てきています。
酒井:
そうなると、社員との軋轢が生まれるケースもありそうですが…。
竹内:
実はあまり起きたことがないんです。
セレンディップグループに入って、「会社も人も成長する」ということを体感してもらうしかないですね。
酒井:
違うやり方を実行してみたらよかった、とスムーズに進む?
竹内:
違うやり方を実行し、慣れてもらうためには、スモールウィンとその見える化が大事だなと思っています。
フォーマット化・透明化で
信用と理解をコツコツ築いていく
竹内:
大きなことって変化が見えづらいですが、1か月単位、3ヶ月単位なら「こんなに変わっていますよ」と見える化できて実感がわきやすい。
給与・賞与など社員の待遇や社内規則などは、変化としてわかりやすい一方で、生産性や不良率など変化していることが分かりにくい分野もあります。そうした一つ一つをきちんと説明し、見える化することで、社員に気づきを与えていくことを心がけています。それに気づけば、小さなwinでも前向きに取り組む人が増えるんです。
また「これをしなさい」ではなく、やる意味や理由を絶対に端折らず「やらないと大変なことが増える」を体感してもらいます。
酒井:
「なんでこんなことする必要があるの?」と、社員はネガティブに捉えがちです。
竹内:
そうならないよう、やらないことによるデメリットを1つ1つ説明していきます。メリットだけを説明するよりも有効だと思っています。
例えば、監査も同様で、「面倒なことが増える」、「できていないことを調査され、つげ口されてしまう」と構えてしまうのが前提だからこそ、「皆さんのコンプライアンス違反を犯してしまうリスクを未然に防ぐのが監査ですよ」と、説明するようにしています。
酒井:
明言してもらえると、安心にも繋がりますね。
竹内:
端的に言えば「改悪はしないから、安心して欲しい」と伝え続けます。逆にうまく機能しないことがあれば意見を吸い上げるようにしています。
ルールを組織に落とし込むためにも、決して伝言ゲームにならず、伝える道筋、仕組みを作るということが重要ですね。

酒井:
僕のクライアントも「当社は伝言ゲームができないんだよ~」なんて苦笑されているんだけど、伝えるって難しいですよね。
竹内:
もちろん小さな混乱はあります。よくあるのが、会議ごとに異なる報告資料を作ってしまうこと。役員会でも、部門内会議でも同じ資料を使った方が作る側の負担も少ないし、伝わることがブレないので1つで行こうよと。
加えて、経営層と従業員が直接対話するタウンホールミーティングも定期的に開催し、役員会で議論した重要事項や会社の業績などブラックボックス化せず、すべて情報公開します。
伝言ゲームがうまくいかない会社は、会議体によって情報を使い分けているのかもしれませんね。
セレンディップは上場しているということもあり、IRで発表した内容は、翌日には従業員に説明会を開催して、主要取引先様にも情報共有をする。これをフォーマットにしています。
酒井:
徹底したフォーマット。
竹内:
会社を透明化し、情報を一元化することにより、結果として従業員にも、取引先にも安心してもらえるようになりました。創業当初は「セレンディップとかっていう会社は本当に大丈夫なのか?」なんて言われましたが(苦笑)、そこから比べるとだいぶ信用いただけるようになりました。
酒井:
それは安心ですね。
竹内:
上場したことのメリットは大きいですね。ネットやyoutubeで資料を閲覧することが可能ですし、裏取りができますからね。
酒井:
なるほど。その上で1日目に「透明性を確保します」と言い切るのは信用に繋がりますね。
竹内:
やはり会社は社員のものだと思っているので、より良くなるよう改善したい。根幹は業績の向上ですが、その他にも開発や品質など、社員やその家族がプライドを持てる会社にしていきたいと思っています。あとこれは僕らのコンセプトでもあるのですが「家業が企業になる」ということをお伝えします。
酒井:
家業から企業へ。具体的にはどのように変わってくるのでしょう?
竹内:
オーナー一族の会社から、社員全員の会社になるということですね。
酒井:
それは社員さん1人ひとりに響くでしょうね。
竹内:
圧倒的な違いを感じると思います。
上場したことでより透明化され、名実ともに社員全員が株主でみんなの会社ですよと。意見も言えるし、私が社員や株主の皆さんへの約束を違えたら糾弾もできますから「それ嘘じゃないですか」って言ってくださいねと。
酒井:
はっきりとお約束されているのですね。
竹内:
言いっぱなしが通らないのは経営者としてはプレッシャーにもなりますが、従業員の皆さんとはフェアな関係でいられる。
家業から企業になることは大きな傷みも伴うけれど、みんなの中から社長を選び、共感する人がついていくのがいいのではないかと。
酒井:
むしろロマンすら感じますね。
対して「オーナー家と同じ苗字の人しか役員になれない会社」もありますよね。「会社にいるのはオーナー家の一族とそれ以外の人。それ以外は部長だろうが新人だろうが皆同じ」みたいな。そうなると野心のある人にとっては働きたくない環境になる。

竹内:
日本では古来より家父長制度があり、家督の相続は男性、とりわけ長男が引き継ぐことが当たり前とされてきましたが、欧米の会社は大きく異なります。例えばポルシェなどはオーナーが大株主として存在するけど、経営しない。いわゆる「所有と経営の分離」は珍しくないんです。
日本は所有と経営が一体化しているので、オーナー=社長で、役員も親族で固めてしまうというのが一般的ですが、もう少し柔軟になればと思います。
酒井:
プロパー社員に経営を任せるネックはそこだよね…。
竹内:
今まではそれが責任感や義務感であったり、同族経営だからこそうまくいくと信じて疑っていなかったわけですが、そろそろ成り立たなくなると感じています。
少子化による後継者不足であったり、また職業選択の自由度が高まっていることも理由の一つです。
東京の大学を出て、就職を考えたときに、最先端のIT企業や外資系企業など選択肢がたくさんあるのに、田舎に帰って利益率が低くて借入が多く、油まみれで、高齢化が進んでいる中小企業なんて継ぎたくないよ…と考えるお子さんのほうが多数派でしょう。昔はご先祖様がおこした会社は「継がねばならぬ」ということで、勝手な職業選びは許されなかったけれど、今はだいぶ緩和されてきました。
今後の中小企業は、会社の将来を真剣に考えることができる経営の担い手に任せる、という第三者への承継を真剣に考えないといけない時期にきていると思います。
アメリカで学んだM&Aを軸に
日本の良さに合わせ企業の体幹を作る
酒井:
ところで貴社は解決したい社会課題として「経営者の高齢化」「日本のマーケット縮小」「生産性の低さの改善」など日本の中堅・中小製造業が成長するための課題5つを上げていらっしゃいますが、これについて詳しく教えてください。
竹内:
これらの課題については、どれも周知の事実でしたが、どこも解決できずにいたことでもあります。その理由としては、人材や資金不足だったり、知識やノウハウがなくてできなかったことです。でも逆に言えば、それさえクリアすれば第二創業のような成長もできる。
どの会社も次世代にバトンタッチしていくわけですが、汚れたバトンでは誰も受け取ってくれません。次世代が受け取りやすい形にして、成長の卵ごと渡さなければならないのです。
酒井:
確かにそうですね。
竹内:
それには付加価値向上はもちろん、生産性や品質を上げることや、またIoT・AIやロボットを活用できる人材を作ることも含まれます。
会社ってオーダーメイドスーツのようなもので、現在の社長にとっては動きやすいけれど、次の社長にとって機能的かどうかはわからない。だからこそ経営の土台を作って、会社の体幹を鍛える。そうすると揺らぎにくくなるんです。
例えば、ホームページひとつ取っても、自動車部品メーカーだと保有設備の名称と性能だけ書いてあって、その会社の強みや技術の高さ、従業員のスキルやノウハウなど具体的な記載がない会社が多くあります。
酒井:
そういうサイト…多いですね(苦笑)。
竹内:
体幹を作るっていうのは、自社の価値や技術力を整理することも含まれます。新規顧客開拓や人材採用を考えるうえで、自社の魅力を伝えることは当たり前なのにできていないところはとても多い。
古いままの営業資料や会社案内、規定や制度など、それらをひとつひとつちゃんとアップデートできれば、会社が今まで以上に魅力的に、また強くなっていくのだと思います。。
酒井:
そういうところから体幹づくりのお手伝いをする。御社が参画会社を愛しているということが充分伝わってきました。
こうした構想はいつから考えていたのですか?
竹内:
僕はサラリーマン時代にオラクルというシリコンバレーのIT企業に勤めていたことがあるのですが、当時、同社は年間約20社のIT企業を買収していました。信じられないことに、ほぼ2-3週間に1社のペースで合併していくのです。オラクルはソフトウェアの会社なので「この技術が欲しい」「この業種のアプリケーションが欲しい」と毎回テーマを持って計画的に買収を進めています。いかにもアメリカらしいと思うのですが。
一方で、日本企業を見渡してみると、オラクルのようにM&Aを積極的に成長戦略に取り入れている企業は極めて少ない。日本電産やソフトバンクなど、一部の企業くらいでしょうか。
そこで僕らは多くの企業を研究し、その中から米国の「ダナハー」というライフサイエンス・医療機器メーカーを参考に「買収と改善」をひとつのビジネスモデルにしていったのです。
酒井:
日本では買収で成長する会社は確かに少なそうです。

竹内:
オラクル時代にも感じていたのですが、M&Aからそのあとの統合プロセスに至るまでが、が実にシステマティックで超ハイペースなんです。
統合初日である、Day1があり、統合プロジェクトのキックオフからウェルカム…と流れていくのですが、面白い経営の仕方だなと。
自社の力だけのオーガニック成長にお金を投下する日本企業よりも、時間や人材、市場シェアを買うM&Aは合理的な欧米企業にとっては当たり前の選択なのです。
酒井:
M&Aはいいとこ取りで、日本ではオラクルのようにはいかないでしょうね。
竹内:
そうですね。M&Aする方もされる方もお互い慣れているので、例え社名やサービス名称が変わったり、開発がストップしたり、リストラが含めれるようなことがあったとしても、滞ることなく進んでいきます。
酒井:
日本とはマインドセットもメンタリティも違いますね。
竹内:
だからこそ、日本風にカスタマイズしていきました。やはり働いている従業員のモチベーションが重要になるので、変革すべき経営課題と残すべき企業文化を必ず明文化し、情報共有するようにしています。
営業部隊、製造現場、バックオフィス…いろいろ改善しましたが、M&A後の統合プロセスの標準化が重要であり、私が一番力を入れてきたことです。
当初は私と創業メンバーだけが我流でそれをやっていましたが、同じようにできる社員が5人10人と増やしていくためにも、標準化をしていったという流れです。
創業最初は私も買収先の社長をやっていましたが、今は社長を任命して、こうしたプロセスを守ってもらっています。
酒井:
在さんが最初の社長を務めたというと、例のパン屋さんですね。
初めての案件で痛感した
人の感情の繊細さと難しさ
竹内:
はい。地方の老舗ベーカリーチェーンでしたが、赤字で、高齢経営者で、後継者のいない、三重苦の企業でした。あの買収が今のセレンディップのM&Aの原型が作れたと思います。
過去の経験から、M&Aや統合プロセスのことをわかっていたつもりですが、いざ日本の中小企業を買収してみると、様々な壁にぶつかりました。特に、一番難しいのは人の感情だと痛感しました。
当初は、オーナーにも、従業員にも、取引先にも、「名前も聞いたことないあなたは何者なの」という雰囲気で、信用も実績もないので心のシャッターは閉じられっぱなしでした。ところがやっていくうちに私たちの真剣度合いが伝わり、少しずつ心を開いて、耳を傾けてもらえるようになって…。時間は思った以上に長かったですが、結果的に半年で黒字化に目処を付けられました。
酒井:
それはすごい。でも人の感情は一番難しいかもしれません。
竹内:
具体的には10ヶ月で単月黒字を出して、12ヶ月目で大手企業に新しいスポンサーになってもらったのですが、今度は「竹内さんいなくなっちゃうの?」って、社員から惜しまれて。M&A当初は「お前たち素人に何ができる?」と拒絶していた従業員や取引先でしたが、1年間さまざまな苦難をともに乗り越えて、お互い変わりましたね。、私としては、次のスポンサーは大手企業で、資本も安定するので、みんなに喜んでもらえると思っていたのに、「捨てられた」に近い感情だったようです。。
酒井:
竹内お父さんと頑張ろうと思っていたのに、次の日新しいお父さんが来るなんて! って感じでしょうね。
竹内:
この経験から、「従業員や取引先のメンタリティは重要なので、売却を前提としないビジネスモデルを作ろう」と考えて、生まれたのが今のスタイルです。ポテンシャルの高い会社を、やる気のある従業員と一緒に改革して、良い会社にしていく。しかも短距離走ではなく長距離走で。
酒井:
短距離と長距離では、走り方も筋トレも全然違ってきますからね。
竹内:
長距離走の場合は、「一緒に頑張ろう!の先にあるもの=絶対的な安心感と満足感」を作っていかなければと。
酒井:
その前は、ドーナツ店やアパレルにも携わっていたと記憶しています。
竹内:
そうですね。このビジネスモデルを確立するまでは、お金だけ出すとか、人も出すとか、試行錯誤していました。上手くいったものも、そうでなかったものもあり、すべてのステークホルダに「約束ができる形」に変わろうと、今のモデルに落ち着きました。
酒井:
長期であれば約束もできますからね。
竹内:
前述のパン屋さんも今なら違う動きができたと思います。
役職は年齢ではなく適正を重視
早く就くほど経験の蓄積が可能
酒井:
ところで、資金は自分たちだけで調達したのですか?
竹内:
最初は共同経営者と個人のお金を出し合いました。最初に買収と売却を繰り返したのは3社くらいで、そこで作った資金をまた会社に投資していきました。
酒井:
お話を伺っていると、もっとマーケットを広げていけると感じるのですが、具体的な計画はありますか?
竹内:
そうですね、私は経営者を輩出していく会社になりたいと思っているんです。社長をしている人はいっぱいいるけれど、「本当の意味での経営者」が少なすぎると感じています。
ありがたいことに、私は外資系企業で若いうちから大きい責任と権限を渡されるという、得がたい経験をさせてもらいました。30代半ばでマーケティング部門の責任者になって、使っていい予算も数10億あって、自分の考えた戦略に則って使える。米国本社としては「権限は渡すけれど、結果も出してね」というシンプルなものでした。私のビジネスパーソンとしての礎は、この時期に形成されたものです。年功序列制の日本企業ではまずできない経験だと思っています。
酒井:
40歳で課長、50歳で部長、55歳で役職定年…というスタイル。

竹内:
セレンディップの社員にも、外資系企業のようにチャレンジできる経験をさせてあげたいと思っています。今当社グループで一番若い取締役は30代前半です。
経営者になるためには、知識も必要ですが、経験値も重要になります。若い時に経営者の一翼を担っていれば、10年もやればベテラン経営者の仲間入りできますから。
酒井:
55歳からだと遅いけれど、35歳から経営者をやれば45歳の時点で10年の実績が積めますよね。
竹内:
和魂洋才というか、日本企業と欧米企業のいいとこどりをしたハイブリッド企業になれればと思っています。年齢や経験、実績、性別を超えてチャレンジできるようなタレントマネジメントの仕組みを作っています。
酒井:
上に立つ人がつくる環境によって、下の成長は変わってきますよね。
竹内:
スポーツなら、よき指導者に巡り会うことが影響するし、企業なら優れた上司と出会うことが影響する。
職場環境さえ違えば成長する有能な人財はたくさんいます。「35歳で取締役になれるなら、自分もなりたい」という人も出てくるでしょう。そうした「新しいあたりまえ」をセレンディップで作っていけたらなと思っています。
私の子供のころは、経営者はおじいさんの仕事だと思っていましたから(笑)。
酒井:
サッカーの中田選手も、幼い頃から世界で通用する選手になると言っていて、それのモデルが「キャプテン翼」だったそうですね。マンガの世界だったとしてもイメージできるのはいいことですね。今、バスケットボールで何人もの日本選手が世界で活躍していますが「スラムダンク」の影響だといわれています。
竹内:
前提が変わる、というインパクトは大きいですよね。
例えば製造業などで、「日本の中小企業はこうだ」というイメージを全く変えるロールモデルを作れば世界と戦えると思います。
若くても経営メンバーとして機能している姿を見せていきたいですね。
酒井:
ドラマの「下町ロケット」なんかもいい例ですよね。自分たちでもできるって勇気が湧いてくる。ましてリアルなロールモデルなら尚更です。
竹内:
はい。私の代で完成できるかわからないですが「M&Aが特別だったなんて懐かしいよね~」とか「40代で取締役になってないなんて」という感覚にできたらと思うとワクワクします。
酒井:
人は「見るものが変わると意識は変わる」と言われます。かつて日本人が黒船を見て意識が変わったように。
竹内:
いつの時代も、ファーストペンギンはリスクばかり指摘されます。が、可能な限り良いと思えることは、当社の仕組みに取り込むようにしています。そしてうまくいった場合は成功事例として「こうやったらうまくいくよ」とロールモデルを作っていけばいいと思っています。
酒井:
セレンディップのやり方は「若くても活躍できるんだ」とか「製造業のモデルだって変わっていい」と、既成概念を覆すものです。それを見たとき「私もこうなりたい」とか「当社も変わらなきゃ」と考える人が続出して、社会はいい方に変わると思います。
竹内:
成長と拡大は目指していますが、いたずらに事業規模を大きくするのが目的ではなく、私たちのやっていることで社会にインパクトを与えて、常識化して欲しいと思っています。
選択肢のひとつの例として知ってもらい「真似してみようか」って行動する人が増えれば、社会全体が変わっていけるのかなと。
酒井:
新しい常識の提示ですね。野茂の大リーグでの成功のような、後に続く人が出てくるようなインパクトですね。
視野を広げ、特性を活かすことで
最適な継承の形は無限大になる
竹内:
当社は現状、第三者継承という立場でのみM&Aをやっているのですが、これを親族内継承でも同様のことができたら世の中にあるほぼすべての事業継承はうまくいくなと思います。
酒井:
確かに、マーケットはとてつもなく大きいですよね。
竹内:
それができるようになれば世の中はもっと良くなるかなと。
したがって、私たちも100%買収にこだわることなく、資本参加の仕方など、実験的にいろいろなスキームでやっています。例えば、先代には株式を私たちに譲渡していただいて、ご子息さんに再出資してもらい、社長兼株主になってもらう。というやり方です。一部オーナーとして権利を維持しつつ、セレンディップとともに成長していくというやり方です。
親族内承継と第三者承継のハイブリッド型になります。どちらがいいというのではなく、両方のいいところを取り入れられればと思っています。
酒井:
では親族内継承とうたってはいないけれど、実際は行っている状態ですね。
竹内:
はい。外部人材が入るのを好まない企業には不向きですが、「子どもだけでは心細い。経営ノウハウを授けてほしい。経営人材を提供してほしい」など、個々のニーズに合わせてやり方を変えています。
酒井:
企業としての体幹が整えば、頼もしい会社になりますね。
竹内:
親族内継承だからこそうまくいくこともありますが、一方で近い関係だからこそトラブルが多くなることもあります。
そうした意味では、共同経営が成長にもリスクにもコミットする形が一番合っています。
酒井:
以前、上場企業の収益力の統計を調べた時、一番高いのは創業者がそのまま社長になる時、2番目が娘婿の継承、3番目は直系家族の継承、4番目がプロパー社員による継承とありました。
なぜ娘婿が2番目かというと、直系家族に比べ娘婿は選べるからハズレが少ない。在さんの話を聴いていると、セレンディップが娘婿になる感じですよね。
竹内:
嬉しいお言葉です。そもそも、創業者と同じような優れた経営者になること自体、難易度が高いわけで、さらにこの経済や市場環境では、会社を成長させていくのは至難の業です。
その中で、会社を持続的に成長させていくためのパートナーとして、セレンディップが大きな選択肢になっていきたいですね。

酒井:
とても理想的だと思います。
周りを見ていても、確かに株は売らなければ現金にはならないけれど、株価で計算すると資産家と呼べる人はいますね(笑)。
竹内:
株式を上手く使いこなせると、成長戦略の選択肢が増えます。多くの経営者は間接金融いわゆる金融機関からの借入れに対する知識はありますが、直接金融いわゆる株式や債券による資金調達の知識が少ないのが現状です。上場、未上場にかかわらず、借入以外の効果的な資金調達ができないことには、成長戦略を描くことはできません。
これはオーナー個人としても同様で、株式を売却し、一部現金化することで、より豊かなワークライフバランスを築くことも可能になります。老後の資金や早期リタイアの後の余暇と、使い方はそれぞれですが、もっと株式を上手く活用できるといいなと思います。
土地やお金という形ではなく
「教育」という形で財産のバトンを渡したい
竹内:
いろいろ話してきましたが、私自身は自分の子どもに会社を継いでほしいとは考えていません。
というのも、私自身、先祖から土地やお金もしくは会社という単位ではなく「教育」、言い換えると、「知の継承」をしてもらいました。
いわゆる大学などの高等教育だけでなく、生き様や人生観を教育=知の承継という形で受け継いだように感じています。
酒井:
在さんのご先祖は、確か小松製作所の創業者でしたよね。
竹内:
はい、竹内明太郎は曾祖父にあたるので、僕で4代目になります。曾祖父は政治家であり、事業家でもあったわけですが、彼の信念として「工業富国基=工業こそ富国のもと」という考えを強く持っていました。幼少期よりその考えに触れることが多くあり、私の原点になっていますね。
酒井:
工業立国を目指されていたというわけですね。
竹内:
そうなんです。曾祖父はパリ万博で日本と諸外国の著しい差を感じたことがきっかけだそうです。鉱山経営や小松製作所以外にも、日本初の自動車メーカーである快進社(ダットサン)への出資など、新たな工業化の幕開けを作った人物です。
前述した「教育を残す」という意味では、早稲田大学理工科や高知工業高校など、資金や人材を提供し、設立に尽力しました。


酒井:
財産として残してもらった教育を次世代に伝える…。
竹内:
セレンディップで実現できていることはまだまだ小さいことですが、成せることが大きくなればその影響力も違ってくる。当社ではIR情報も公開していますから、セレンディップのビジネスモデルもぜひ参考にしてほしいと思っています。
学校作るまではいかないですけれど、もっと多くのことを次世代に伝えていけたらなと思っています。
酒井:
とはいえ、在さんは大学でも教えていらっしゃいますよね。
竹内:
ええ。事業構想大学院大学で客員教授をさせていただいています。企業経営と教育の両立は大変ですが、会社を大きくするだけではね…。人に教えるということは、自分の考えやノウハウを体系化することでもあり、学術的にブラッシュアップすることにもつながり、さらには生徒と対話することで新しい気付きを得ることもできます。
酒井:
明太郎さんの「養成は将来を考えて努めて多く、儲けはその次でよい」というお言葉と同じですね。
竹内:
はい、そうありたいです。自身の指針にもなりましたし、先祖にこういう生き方の人がいたということで、いろいろな教育を受けられたので、自分も教育で還元していきたいですね。
セレンディップ自体が経営者養成機関として、うちで得たものを使って他社で活躍してくれたら嬉しい。
また、私自身、酒井さんの経営コンサルタント門下生として、当時僕は29歳でしたが、コンサルはおろか提案書も書いたことがなくて(苦笑)。酒井さんには多くを教わりました。
酒井:
当時のコンサルは、ロジカルな報告書や資料を作り「こうしたらいいですよ」というのを伝えていましたが、在さんは当時から現場でコーチングを多用してクライアントにバンバン問いを投げて、見ていて面白いなと思いましたよ。
竹内:
いえ、生意気でした(苦笑)。
酒井:
いろいろな企業さんで研修したり、楽しかったですよね。
竹内:
酒井さんに出会って、経営とは、商品開発とは…ということを初めて意識しました。気付きがありましたね。それがなかったら今頃何をやっていたのだろう…と思う時もあります。
酒井さんのおかげで、経営やマーケティングの面白さを感じることができました。
酒井:
当時の東海総研にはユニークな人がいっぱいいましたね。このインタビューの第1回目は、在さんが在籍された頃に理事長だった水谷研治先生でした。当時から「楽しいと思うことはどんどんやりなさい」とおっしゃってましたが、今も同じことをおっしゃっていました。
竹内:
水谷先生をはじめ、当時ご一緒したみなさんは、どの方もすごく優秀でしたね。
酒井:
こうして在さんも会ってくれるし、皆さんの活躍が嬉しいですよ。優秀な部下に恵まれて幸せです。感謝しています。
竹内:
いえいえ私の師匠ですから…いうなれば酒井経営塾の門下生ですからね、通知表を見られているようで恥ずかしいですね(笑)。
酒井:
そういえば、今の在さんのお仕事仲間も、東海総研が出会いの場でしたね。

竹内:
本当に出会いと気付きと変化がある楽しい職場でした。「どんどんやりなさい」という組織は、人を結果的に育てられると思うんです。それは決して放任ではなくて。
僕も当時の経営陣に新事業の企画書を出しても、反対されなかったし、むしろ面白がってくれた。
でも逆の立場なら…成功の確率はどれくらいになる? なんて訊いたりして、あんなふうにドンと構えていられなかったでしょうね。
酒井:
在さんは、充分波紋を作ってその後のメンバーに良い影響を残してくれました。僕がやりたかった「若い人が活躍できる会社作り」をとっても大きなスケールでやっていて、今日は本当に勉強になりました。たくさんお話しいただきありがとうございます。今後のご活躍も楽しみです。
竹内:
こちらこそ、素晴らしい機会を作ってくださりありがとうございました。

プロフィール
竹内 在(たけうち あり)
セレンディップ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長兼CEO
米国Bradford大学マネジメント学部卒業。
ニフティ株式会社の経営企画担当として、インターネット市場の黎明期に、経営計画策定や市場・競合分析、CI/ブランディングなどの業務に従事。
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社にて、経営・マーケティング戦略のコンサルタントとして活躍。
その後、日本オラクル株式会社のマーケティング本部長に就任。マーケティング戦略の立案から製品のプロモーション展開、市場・競合分析など、潜在顧客の掘り起こしと需要の喚起を中心としたマーケティング活動を推進。 現在は、セレンディップ・ホールディングス株式会社の代表として、子会社の経営にも従事。