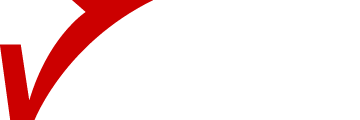弊社ではお客様の要望に応じ、階層別の社員研修を行っています
部長・課長・係長・主任など、組織が階層に分かれているものの、
役割分担が不明確で、組織が機能不全を起こしている会社に対し、
階層別の役割を認識させる研修を実施します。
- 幹部クラスには主に問題発見と課題解決力を身に付ける研修をします
- 部長クラスには主に問題発見と理念共有の風土作りの研修をします
- 課長クラスには主に問題解決とリーダーシップを教育します
- 係長クラスには主に計画立案とプロジェクトマネージメントを教育します
- 主任クラスには主に後輩育成とコミュニケーションスキルを教育します
近年、役員研修・管理職研修として、Z世代とのコミュニケーションを学ぶカリキュラムへのニーズが高まっています。
若手の採用、定着、育成に必要な考え方やコミュニケーション方法を学びます。
階層別研修の対象
研修の内容はお客様の目的に応じ、カスタマイズします。
そのため、時間・参加者数等はお客様との打ち合わせの上、研修の内容を企画書にまとめて提案します。
下記はその元となる階層別・目的別社員研修の代表例です。
- 役員・幹部(次長以上)研修
- 管理職(課長)研修
- リーダー(主任・係長)研修
- 生産性向上体験ゲーム研修
これ以外にもご要望に合わせ、オーダーメイドで提供することができます。
お気軽にお問い合わせください。
講師料
研修講師料の基準は以下のとおりです。
- 1日研修…300,000円(税別)約6時間から8時間
- 半日研修…200,000円(税別)約3時間から4時間
に準備費を加えたものになります。
(交通宿泊費は別途実費ご負担ください)
講師
原則 弊社代表 酒井英之が行います。
なお、テーマによっては弊社パートナーコンサルタントが行うこともあります。
役員・幹部研修

役員は、管理者ではありません。幹部です。
役員に最も必要な力は2つです。
第1は、全社的・長期的な視点から見た問題発見力。
第2は、その問題を解決できる仕組みをつくることです。
当社の役員研修では、この2つこそが自分たちの仕事だと気がつかせ、自分たちで問題を発見し、自分たちで解決する研修を行います。
社長のお悩み事例
- 社長から支持されたことは一生懸命やるが、役員からの進言が少ない
- 幹部が自部門の課長のようなばかりしていて、会社全体を見ていない
- 部門間連携が弱く、他部門のことには無関心な幹部が少なくない
- やがて後継者の右腕となる若い幹部候補を育てたい
期待される成果
- 同じ方向を向いて議論することで幹部の中に一体感が生まれます
- 幹部全員が今まで見えていなかった社内の問題に気づきます
- 結果的に社長が指示しなくても、自分たちから動いて問題解決します
- 全社的な視点が身に着き、部門間の連携が良くなります
主なカリキュラム(標準モデル)
| 自 | 至 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 900 | 1000 | トップ | トップからの問題提起 |
| 1010 | 1200 | 講義 | 役員の役割と期待 |
| 1300 | 1550 | 討議 | 問題の洗い出しと真因分析 |
| 1600 | 1650 | 討議 | 真因の発生原因の特定と解決策立案 |
| 1700 | 1800 | 討議 | 取り組むべき課題の選択と最初の一歩決める |
対象人数
12名以下
管理職研修

課長に最も必要な力は2つです。
第1は、チーム力問題を解決するチームマネジント力。
第2は、OJTを中心とした部下育成力。
当社の課長研修では、この2つこそが自分たちの仕事だと気がつかせ、チーム力を高めるマネジメント方法と部下育成法を学びます。
こんな会社にお勧めです
- 管理職の多くはプレイングマネージャーで、プレイのウエイトが高い
- 目標未達成の管理職に理由を尋ねても、言い訳が多いと感じる
- 年上の部下などやりにくい部下が多く、悩んでいる管理職が多い
- 新入社員、中途社員の定着率が低く現場に問題があると感じている
期待される成果
- 管理職として自分に不足している点を認識します
- 言い訳をして逃げるのではなく、問題に立ち向かうようになります
- 年上の部下や新人との接し方を学び、チーム力が高まります
- 同じ悩みを抱えている者同士が話すことで、前向きな気持ちを引き出します
主なカリキュラム(標準モデル)
| 自 | 至 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 900 | 1000 | トップ | 研修の目的・期待 |
| 1010 | 1200 | 討議 | モチベーションの高い組織を作るポイント |
| 1300 | 1450 | 討議 | 風通しの良い組織をつくる方法 |
| 1500 | 1620 | 討議 | 効果的、効率的に仕事を行う課長の着眼点 |
| 1630 | 1730 | まとめ | まとめと今後に向けた活動の整理 |
対象人数
16名以下
リーダー(主任、係長)クラス研修

課長に最も必要な力は2つです。
第1は、部下や後輩を引っ張っていくリーダーシップ
第2は、上司や部下、顧客等とのコミュニケーションスキル
当社のリーダー研修では、この2つこそが自分たちの職務だと気がつかせ、リーダーシップとコミュニケーションスキルを学びます。
こんな会社にお勧めです
- 今のリーダークラスに将来を担う管理職、幹部になって欲しい
- これまであまり研修して来なかったので管理職が育っていない
- 部下を持つことでストレスを感じているリーダーが多い
- リーダークラスを外部研修に行かせるが、効果が感じられない
期待される成果
- リーダーとしての期待役割を自覚して行動するようになります
- チームの大切さを理解し自分のチームをまとめるようになります
- 部下や後輩に積極的に声がけするようになります
- 個人的に悩んでいたポイントの答えを確実に手に入れます
主なカリキュラム(標準モデル)
| 自 | 至 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 900 | 1000 | トップ | 研修の目的・期待 |
| 1010 | 1200 | 討議 | リーダーシップとは何か |
| 1300 | 1450 | 討議 | 部下や後輩のモチベーションの高め方 |
| 1500 | 1620 | 討議 | 部下のほめ方、叱り方、伝え方 |
| 1630 | 1730 | まとめ | まとめと今後に向けた活動の整理 |
対象人数
20名以下
御社の課題や現状に合わせ、
内容をカスタマイズいたします。
まずは、お気軽に
ご相談・お問い合わせください。