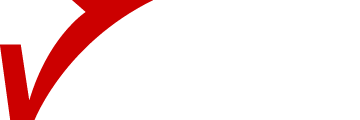vol.393【Withコロナ時代の社長の悩み~Q&A集~】
【Withコロナ時代の社長の悩み~Q&A集~】
Withコロナに徐々に慣れてきましたが、
誰もが「これから」を考えるタイミングになりました。
この一週間に、私はオンラインで3度、
「コロナ禍で社会はどう変わるか?
社長は何をするべきか?」を
テーマにしたセミナーを開催しました。
どの講義も質疑応答の時間が多めにとってあったので、
多くの受講者(主に社長)から質問を頂戴しました。
それらの質問には「今、経営者が直面している課題」が
鮮明に出ていました。
同じことで悩んでいる方も多くいると思います。
また、誰かの質問は、他の誰かの勉強になります。
そこで、本メルマガでは今週と来週の
2回に分けて、セミナーでいただいたQ&Aをお送りします。
今週のテーマは
「コロナ禍を機に経営理念、ビジョンを考える」です。
Q:わが社には「社会の公器」という理念がありますが、
ビジョンはありません。最近はこの理念に従って
地域の人のお役に立つことを探して行ってきました。
やるべきことが見つかり、理念があって良かったと思っています。
これから後付でもいいので
ビジョンを考えていけばよろしいのでしょうか?
A:その通りです。理念に従ってありがとうと言われることに
集中して仕事をしている必ずそこに道ができるはずです。
その道を信じて歩んでいけば、いつか「あれがしたい」という
使命感にたどり着くでしょう。
言葉にするのはそれからでも構いません。
Q:事業承継を考えています。
息子の代では社是は引き継ぎますが、
企業理念を変えても良いのでしょうか?
また変える場合は、息子がブレーンとなる社員と
一緒に創るのが良いのでしょうか?
A:後継者が、今の理念に共感できない場合は、
まず、その理念を先代が制定した背景などを十分に理解します。
それでも変えたい場合は、先代から変えることの許可を得ます。
なぜなら、社員にはその理念が好きだという人が
何人もいるかもしれず、いきなり変えてしまうと
社員がビックリしたりガッカリするからです。
理由をしっかり伝えた上で、変えることが大事です。
また作り方は、社員の意見を聞いた上で作るのが理想です。
ただし、社員に「理念を考えろ」いうわけではありません。
また、「こんな理念を考えたけど、どうかな?」と
言って社員に評価をもらう必要もありません。
大事なことは、社員から理念を考える上で
必要なネタをもらうことです。わが社で働いていて、
どんなときに「楽しい」「やりがいがある」と感じるのか?
こうした情報をアンケートやインタビューで集めます。
すると、理想の会社像が見えてきます。
そして、新理念ができた時に、
「皆さんからこんな話を聞いたので、この理念を創りました」
と言えば、皆その理念に共感するでしょう。
創るのは新社長一人で結構ですが、
その前に社員からネタをもらうところがポイントです。
Q:10年先のビジョンを考えていましたが、
なかなかワクワクするビジョンが描けません。
あまりに夢物語過ぎても人は呆れてしまいますし、
簡単にできることならワクワクしません。
社員がワクワクするちょうどいいポイントは、
どうやって測れば良いのでしょう?
A:皆がワクワクするビジョンには
共通している2つの要素があります。
一つは感動性です。そのビジョンを聞いた時に、
「そうなるといいよね!」という感動が胸の内に起こることです。
感動は「え?」「まさか?」の意外性から生まれます。
ビジョンの中にこれまでの常識を変える要素が必要です。
もう一つは公共性です。
そのビジョンが、社会に良い影響を与え変えていくことです。
感動性が高いビジョンには、
「私も何か手伝いたいと」と人が集まって来るので、
すぐにチームができます。
公共性が高ければ資金調達が容易になります。
今若い人は何かの役に立ちたいと強く思っていますから、
採用も容易になります。
感動性と公共性の二つの要素を含んだ
ビジョンを考えてみてください。
Q:ビジョンは描けたのですが、
実行を誰にやらせるか悩んでいます。
既存の幹部に頼るべきでしょうか?
それとも新しい人たちに任せた方が良いのでしょうか?
A:新規事業は 専任の担当者を立てないと進みません。
担当者が既存事業兼務でやると、
どうしても既存事業の方に軸足が移ってしまって、
新規の方がおろそかになります。
だからといってエース社員を
新規事業の担当にするにはリスクがあります。
そのため新規事業はあまり会社に染まっていない若い人や、
ラインから外れてしまった中年が担当するケースが多いです。
イノベーションを専門とする中央大学の小林特任教授は
「イノベーションはろくでもない社員にしか起こせない」
と言っていますが、正論かと思います。
若手や、ロートル、中途採用者などに期待してみてください。
Q:今、コロナ後のビジョンを考えています。
ビジョンは社長である私が「楽しい」と
思うものであるべきでしょうか?
社員が「楽しい」と思うものであるべきでしょうか?
A:ビジョンは社長が「楽しい」と思うものであるべきです。
そしてその楽しさを社員に伝えてください。
社員にとって辛い仕事でも、
社長の見方や考え方を伝えることで、
その仕事は実はとてもやりがいのあるものだと
感じられるようになります。
それを伝え、同じ価値を感じる仲間を
増やしていくのが社長の仕事です。
Q:コロナ前から脱下請けや多角化の必要性を感じ
何度かトライをしてきました。
しかしながら、きっかけがなくなかなか前に進みません。
突破口はどのように見つけたらよいでしょうか?
A:展示会に出かけられるとよいでしょう。
まず、自分の会社の強みとなる技術を
「○○ができる」「××を□□に変える」というように、
動詞で定義します。次に展示会に行きます。
展示会はこれから伸びそうな市場の展示会を選びます。
そしていろんなブースを見ながら、
「当社の技術を使ったらもっといい商品になるのに」
という商材を探すのです。
見つかったらブースの担当者と名刺交換し、
後日当社の技術を提案にしたい旨を申し出ます。
このやり方で新たな市場を開拓することができます。
展示会が再開されましたら、「犬も歩けば棒に当たる」を
信じて是非行動を開始してください。
(Q&Aここまで)
貴重な質問を頂いた皆様、
またセミナーにご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
次回はコロナ禍で「働き方やマネジメントがどう変わるか?」
の質問への回答を掲載します。お楽しみに!